【中2理科】茎・根のつくりとはたらきの要点まとめです。
茎・根のつくりとはたらき
茎のつくりとはたらき、維管束のつながり、根のつくりとはたらきについてです。テストでも出題率が高いところです。しっかり身につけていきましょう。
茎
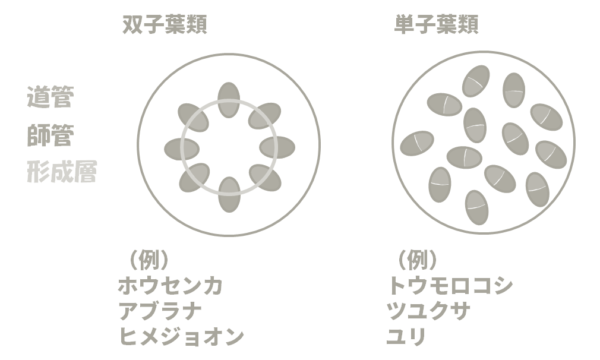
- 道管…根から吸収した水や水に溶けた無機養分の通り道。
- 師管…葉でつくられた養分(有機養分)の通り道。
- 維管束…道管と師管の集まり。 茎の維管束は葉につながり、葉の維管束を葉脈といいます。
茎のはたらきは、植物の体を支え、根から吸収した水や無機物と、葉でつくられた養分が移動する通り道になっています。
茎のつくりを調べる実験
<手順>
- 着色した水を三角フラスコに入れ、植物をさし、水を吸わせます。
- 着色した植物の茎を、輪切りにしたり、縦に切ったりして、顕微鏡で観察します。
<結果>
- 茎の内部で、着色した部分を着色しなかった部分がある。
- 茎の内部で、着色した部分の並び方にちがいがある。
<考察>
- 菊の内部には、吸収した水が通る管がある。
維管束のつながり
茎の維管束は、根の維管束ともつながっています。茎の維管束の並びは植物によりちがっている。
- 輪のように並ぶもの (例)ホウセンカ、アブラナ、ヒメジョオン。根は、主根と側根からなり、葉脈が網状脈のものがある。
- ばらばらのもの (例)トウモロコシ、ツユクサ、ユリ。根は、ひげ根をもち、葉脈が平行脈のものである。
根
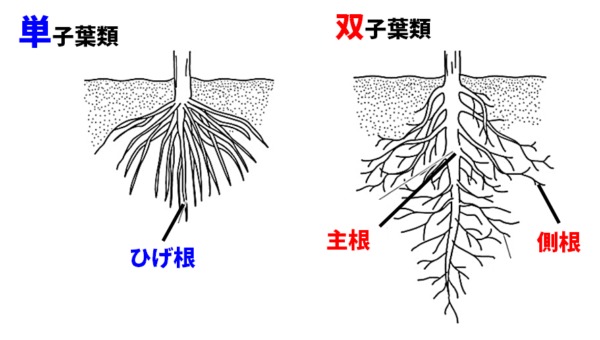
主根と側根
茎から直接のびた太い根を主根、主根から出る細い根を側根といいます。(例)アブラナ、ヒマワリ、タンポポ、ナズナ
ひげ根
ひげ根は、茎の根もとから広がるたくさんの細い根。(例)ツユクサ、スズメノカタビラ、イネ、ヒヤシンス
根毛
根毛は、根の先端近くにある。細い毛のようなつくりです。根毛によって、土にふれる面積が大きくなり、水や水に溶けた無機養分が効率よく吸収されます。

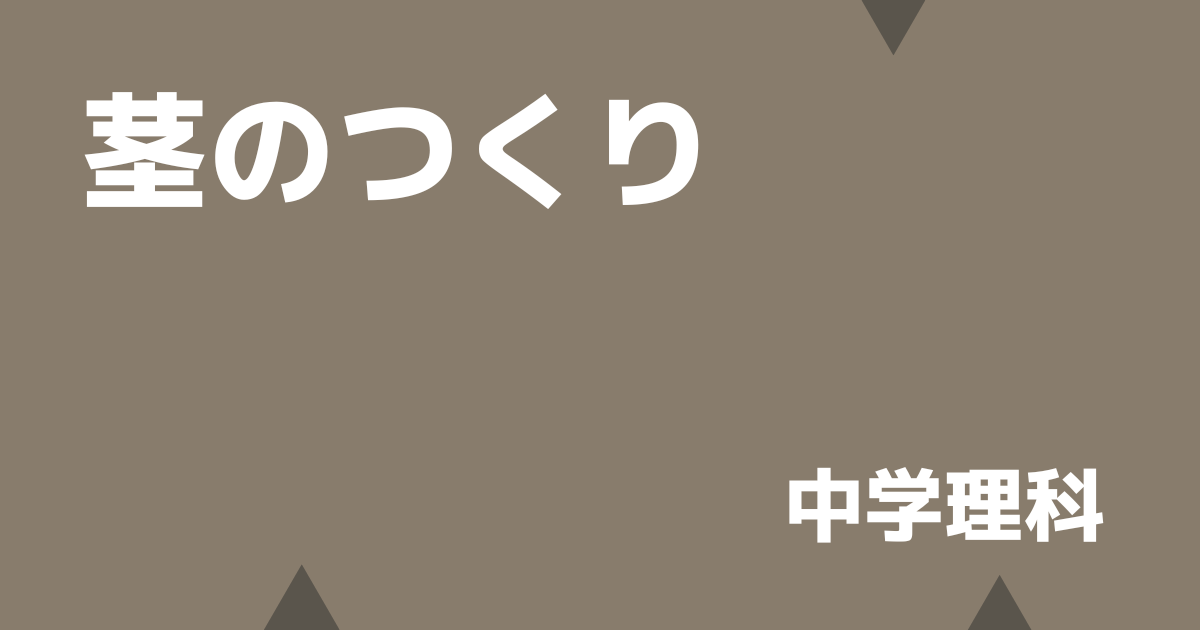

コメント