中学地理「アジア州」についてまとめています。アジア州について、地形や文化、気候、工業、日本との関係などにもふれています。それでは、中学地理「アジア州」です。
アジア州の概要

アジア州は、広い範囲に及びます。アジアとどのような地域かというと、ユーラシア大陸の広い範囲をしめます。地域区分として、東アジア、東南アジア、南アジア、中央アジア、西アジアなどです。
地形は、日本からインドネシア東部まで、火山や地震の多い島々が並びます。インドネシアからヒマラヤ山脈をへて、ヨーロッパ州のアルプス山脈まで、高く険しい山地が東西に連なります。
- 季節風(モンスーン)…アジアの北部と南部でよくふきます。夏と冬で向きが逆になる風。沿岸部に強い影響を与え、海から湿った風によって雨が多く降る雨季と、内陸から乾いた風によって雨が、ほとんど降らない乾季が現れます。
- 乾燥した地域…大陸内部から西アジアにかけては、太平洋やインド洋からの風の影響を及ばず、乾燥した気候の地域が広がります。
多様な文化と集中する人口
交流で生まれたのが、アジアの文化です。アジアの民族の文化的特徴は、多様で同じ地域に多くの民族が暮らすこともあります。各地の文化は、他地域との交流を通して発展し、中国やインドの文明は、東アジアや南アジアの文化に大きな影響を与えました。
西アジアで生まれたキリスト教やイスラム教など宗教や文化も、アジアとヨーロッパを結ぶ交易路を通じて広まりました。
アジア州は、世界の人口の約6割が集まります。農業が盛んな東アジアや南アジアの平野部を集中し、山脈や乾燥の厳しい中央アジア、西アジアに少ないです。
アジアの人口は、衛生・栄養状態が大きく改善された20世紀後半に爆発的に増加しました。一方で、都市への過度な人口集中が問題化した国もあります。
中国では、人口が世界最大の国ですが、工業の発達した沿岸部に集中していて、開発が進んでいない内陸部から働きに出る働きもあります。政府は、人口の移動されるとともに、人口そのものをおさえるため、一人っ子政策を推進してきました。人口の9割は漢民族ですが、少数民族の住む地域に自治区を設置しています。
アジアの農業
アジアの農業は、降水量と関係が深いです。
- 水田での稲作中心の地域…季節風(モンスーン)の影響で、降水量が多い東アジアから南アジアの平野部。主食は米となります。
アジアの米の生産
- 米の生産…世界の米の8割以上をアジアで生産しています。中でも人口が多い中国、インドでの生産量が多いです。
- 米の輸出…東南アジアのタイ、ベトナムで多いです。
畑作
降水量が多くない中国北部やインド西部などは、小麦・トウモロコシ・綿花などを栽培します。アジアは、小麦の生産に多いですが、米と同様、多くは、国内で消費され、輸出量が少ないです。
牧畜
西アジアや中央アジアでは、乾燥に強い羊やラクダなどを飼育し、乳や肉を食料にしています。遊牧を行う地域もあります。しかし、地下水や大きな川の水を利用できるオアシスでは、小麦、野菜、果物などの栽培をしています。
中国の農業
中国では、経済発展で消費が増えた肉類や家畜の飼料の輸入が増加しています。
アジアの工業
工業化と外国企業の進出が進んでいます。
- 工業の発達した国々…東アジア、東南アジアには韓国やシンガポールなど、工業の発達した国々があります。雑貨・衣類などから、高い技術力が必要な電気機械などを輸出する国へと発展しました。
タイ、マレーシア、ベトナムなどでは、工業団地に外国企業を受け入れ、労働者が勤勉で賃金が安く、人口が多い国々に近いため、日本やアメリカ合衆国などの企業が進出しています。
東南アジア諸国連合(ASEAN) などアジアの国どうしの貿易が盛んです。自動車やパソコンなどの部分生産を国々が分担する動きが見られます。また、インドのIT産業など新たな産業もあります。
- 石油資源が豊富な西アジア…サウジアラビア、イランなどは、豊富な原油や石油製品で経済発展しました。
中国の工業
1980年代から経済特区などが設けられ、賃金の安さに注目した外国企業の進出が相次ぎ、急速に工業化しました。「世界の工業」と呼ばれています。一方で、沿岸部と内陸部の経済格差が生まれています。
アジアの変化
日本の輸入品からみたアジアにおいて、日本の貿易の約6割はアジアの国々が相手となっています。アジアからの輸入品は、かつてはエネルギー資源や農林水産物が中心でしたが、1980年代以降、東アジアや東南アジアの工業化により変化が見られます。
日本の文化から見たアジア
漢字や仏教は、中国や北朝鮮から日本に伝えられました。アジアと日本の結びつきにおいて、仕事や環境による人の行き来が増え、インドからコンピュータ技術者のように先端技術に関わる例も増えています。今後も日本は、アジアの一員として関係を深めることが大切です。
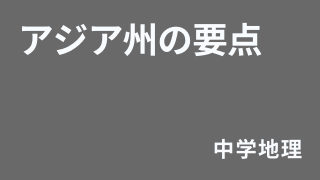
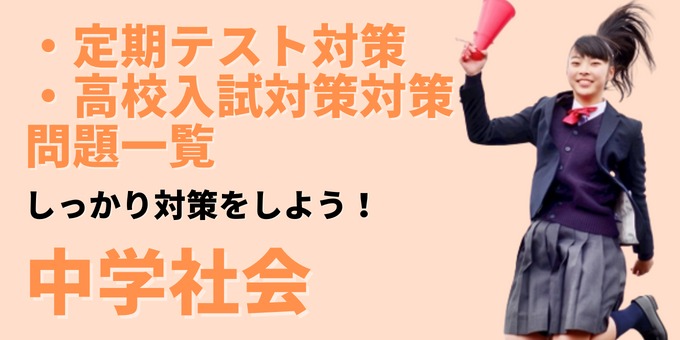
コメント