中3理科の「斜面を下る運動・自由落下運動」についてまとめています。斜面を下る運動・自由落下運動は、速さが増加する運動ですが、速さが減少する運動や速さや向きが変化する運動までふれています。それでは、中3理科「斜面を下る運動・自由落下運動」です。
速さが増加する運動
物体の運動の向きと同じ向きに力がはたらくと、物体の速さは増加していきます。
斜面を下る運動
斜面上の台車には、斜面にそう下向き(運動の向き)の力がはたらき続けるため、台車の速さは時間とともに増加します。また、斜面の角度が大きいほど、台車の速さの増え方が大きいです。これは、斜面の角度が大きいほど、台車にはたらく重力の斜面にそう分力が大きいためです。
自由落下運動
物体を落下させたときの運動。自由落下する物体の速さは、物体が斜面を下るときと同じように、しだいに増加します。これは。物体に一定の重力がはたらき続けるためです。
斜面を下る台車の運動実験
<手順>
- 斜面に台車を置き、台車にはたらく斜面にそう力の大きさを、斜面上の3か所ではかります。
- 台車の斜面上での運動を記録タイマーで記録します。
- 斜面の角度を変えて、1,2と同様に実験します。
<結果>
| 場所A | 場所B | 場所C | |
| 角度5° | 0.8 | 0.78 | 0.79 |
| 角度10° | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
- 0.1秒(5打点または、6打点)ごとにテープを切って、左から順に下端をそろえて台紙に並べてはる。
<考察>
- 台車にはたらく斜面にそう下向きの力は、斜面のどこでも同じで、斜面が急なほど大きいです。
- 台車の速さはしだいに増加し、その増え方は斜面が急なほど大きいです。
真下に落下する物体の運動(自由落下運動)の実験
- 真下に落下する運動は、斜面の傾きが多くなって、90度になったときと考えることができます。
- 1のことから考えることができるように、斜面上の運動よりも下向きの力が大きくなるため、速さの増え方は、斜面上を運動させるより大きくなります。
- 空気抵抗を考えなければ、物体の落下する速さの変化のしかたは、物体の重さによって変わりません。
速さが減少する運動
物体の運動の向きと逆向きに力がはたらくと、物体の速さは減少していきます。
斜面を上る運動
球が斜面を上るときは、球の運動の向きと逆向きに力がはたらくため、球はしだいに遅くなり、一瞬静止したのち、下り始めます。
摩擦がはたらく運動
運動の向きと逆向きの力(摩擦力や空気の抵抗など)がはたらく場合、物体のしだいに減少し、最後に静止をします。
速さの向きが変化する運動
運動しているテニスボールをラケットで打つときなど、力がはたらく物体の運動では、その速さや向きが変わります。
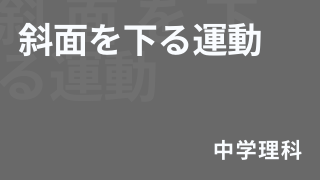

コメント