中3理科の「等速直線運動と慣性の法則」についてまとめています。等速直線運動と慣性の法則のほかに。作用と反作用などにもふれています。それでは、中3理科「等速直線運動と慣性の法則」をみていきましょう。
等速直線運動
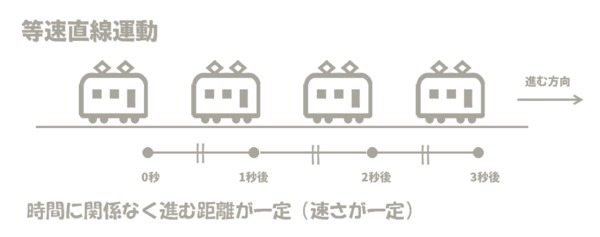
等速直線運動は、速さがかわらず、一直線上に動く運動です。運動している物体に、その運動の向きに力がはたらいていないとき、物体は等速直線運動をします。
等速直線運動の時間・速さ・距離の関係グラフ
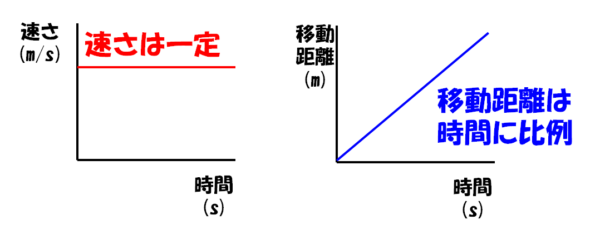
- 時間を横軸、速さを縦軸にとってグラフをかくと、横軸に平行な直線になります。
- 等速直線運動をする物体のグラフは、原点を通る直線になります。移動距離は時間に比例します。
力がはたらかない運動実験
水平な台の上を運動する台車を調べます。
<手順>
記録タイマーのスイッチを入れ、台車を手のひらでポンとたたき、運動を記録タイマーで記録します。テープの記録をもとに次の1~4の処理を行います。
- テープ5打点(または6打点)ごとの台車の進んだ距離をはかり、表に記入する。
- テープ5打点(または6打点)ずつ切って、台車に並べてはる。
- 台車の速さと時間の関係をグラフにする。
- 台車の進んだ距離と時間の関係をグラフにします。
<結果>
| 打点(打) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 距離(cm) | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
- 時間と距離は比例し、時間が経っても速さは一定。
慣性の法則
慣性の法則とは、「物体は外から力を加えない限り、製糸しているときはいつまでも静止し続ようとし、運動しているときはいつまでも、等速直線運動を続けようとする」法則のことをいいます。物体のもつこのような性質を「慣性」といいます。すべての物体は慣性をもちます。
<例>
- だるま落とし…力を受けた部分だけが横に動き、他の部分は落下します。
- バスの発射…発車のとき、状況は静止の状態を続けようとして、後ろに傾きます。
- バスの停車…停車のとき、乗客は運動の状態を続けようとします。
力がつり合っているときの運動
運動している物体に力がはたらいている場合でも、それらの力がつり合っているときは等速直線運動をします。
- (例)一定の速さで走行する自動車では、エンジンの力と摩擦力などがつり合っています。
力をおよぼし合う運動
2つの物体の間にはたらく力…2つの物体の間にはたらくとき、たがいに向きが反対で大きさの等しい力がはたらきます。

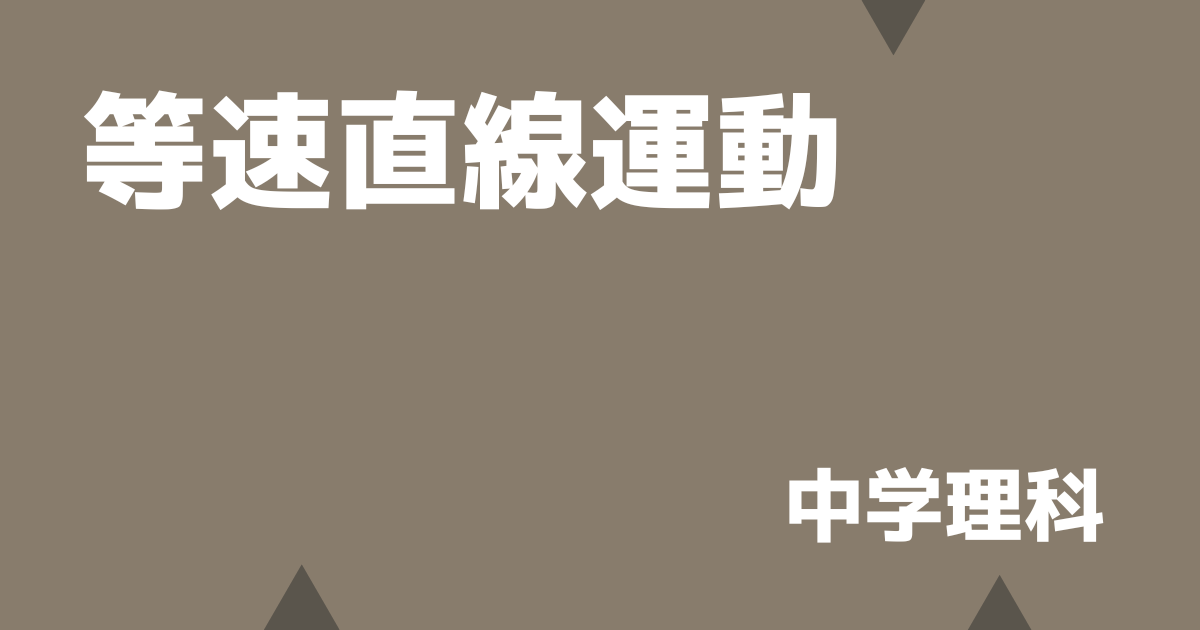

コメント