【高校入試対策国語】作文の書き方と構成の仕方出題形式(種類)に応じて、書き方の切り口が変わってきます。そのあたりについて、詳しく記述しています。
作文の書き方の要点
作文とは 与えられた課題に基づいて文章を書くこと、またはその文章のことである。高校入試対策では、課題が与えられ、その課題には通常、条件が決められています。こういった課題作文では、主題(内容)に合わせて題材をそろえ、指示された段落構成、字数などを守って書くことが重要である。
- 原稿用紙を正しく使う。
- 語句を適切に使い、正しい表記法と言葉のきまりにしたがって書く。
- 与えられた条件にしたがった内容・構成・分量て書く。
がポイントです。
作文を書く手順
- 条件をつかむ。(指示された内容・構成・分量などの条件を確認)
- 主題(内容)を決める。(あらかじめ題が決まっている場合、その意図をとらえて主題を決める。
- 題材を集める。(主題(内容)に関わりのある経験、 見聞などを書き出す)
- 構成を考える。(書き出し→展開→結びを意識。二段落構成なら、具体例と考えなど。)
- 実際に書く。(原稿用紙の使い方に気をつける。)
- 見直して推戴する。(推敲の観点をおさえる。)
作文メモを作る
思いついたことを箇条書きにする。順不同でよい。
- 主題…自分が伝えたいことを短文で書く ・
- 題材…具体的な事実・実際に起きたこと・自分や他の人の行動、言葉・自分の感想、考え
作文の構成の要点
制限字数によりますが、中学の定期テストや高校入試で多い600字程度の作文では、三段落構成とし、「主張(自分の意見)」→「理由・根拠」→「まとめ」となります。ただし、都道府県によっては、あらかじめ「この構成(型)や流れ」で書きなさいと指定する場合もあるので気をつけておきましょう。
- 第一段落…自分の意見(主張)最も言いたいこと
- 第二段落…そう考える理由や、具体的事例をあげて記述していくこと
- 第三段落…終わりとして、まとめを記述する。
第一段落(主張)
作文はいわば、「自分の考え」を記述していくことです。その「自分の考え」をずばり第一段落に記述します。テーマ・題材にに対して、「こう考える」という、「自分の考え」 をはっきり表すことが最も大切だから、最初に記述するということです。これなら、自分の考えがはっきりと読み手に伝わります。この第一段落に、理由や根拠などを記述してだらだらと長くするのは避けましょう。何を言いたいのかわからなくなります。
第二段落(根拠)
第二段落では、「理由」や「具体例」は自分の考えにそったものを記述します。第一段落で「こう考える」と記述しています。第二段落では、「それにはこんなわけがある」の形の、「こんなわけがある」(こんな事実がある)ということを記述していきます。
根拠や理由に「具体的な事例」をとりあげると説得力が増します。その具体的事例は、「事実」にあまりこだわらなくてもいいです。テーマや題材によっては、省略してもいいし、創作をしてもいいです。 例えば「水泳が好きだ。」と主張して、「気が向いたときに、一人でやれるからだ。」でも十分な理由となります。
根拠や理由を記述する上で、大切なことは、「自分の考え」と矛盾しないということです。
第三段落(まとめ)
「まとめ」は第一段落の主張を言いかえて記述していく、最後のしめくくりです。第一段落「こう考える」→第二段落 「こんな理由がある。」→第三段落「だからこうしていきたい」といった流れです。前向きに「こうしていきたい」と結びましょう。
段落構成では、読む人にわかりやすく伝えるためには、文章の構成を工夫することが大切である。
二段落構成の例
- 第一段落:体験・見聞
- 第二段落:感想・考え・意見
三段落構成の例
- 序論(書き出し):問題提起
- 本論(展開):体験・見聞
- 結論(結び):意見のまとめ など
文章の構成
意見を述べる文章では、自分の意見をどのように示すかによって、文章の構成が変わる。
- 頭括式…意見・根拠(初めに意見を述べ、あとに根拠を示す。)
- 尾括式…根拠・意見(初めに根拠を示し、あとに意見を述べる。)
- 総括式…意見・根拠意見のまとめ (意見を示してから根拠を述べ、最後に再び意見をまとめる。)
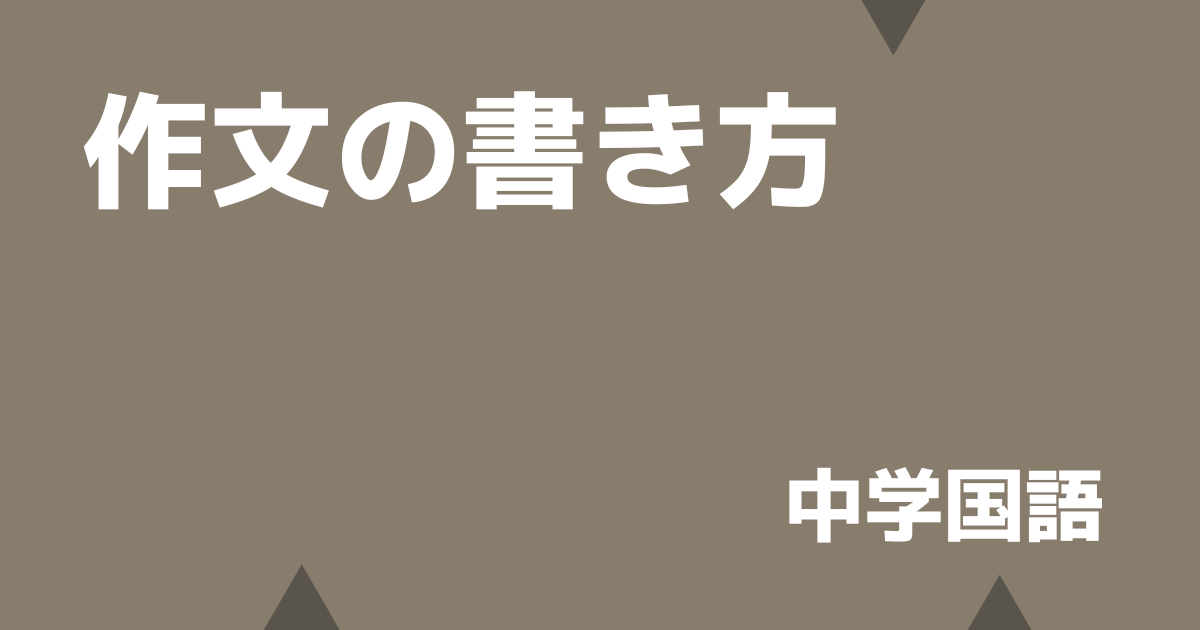

コメント