中学国語・古文「主語・助詞の省略の見抜き方」についてまとめています。
古文の省略
ここがポイント!
【1】主語や目的語につく助詞「が」の省略
(例)今は昔竹取の翁にといふものありけり
<訳>今となっては昔のことだか、竹取の翁という人がいた。
「もの」のあとに、「が」が省略されていた。
【2】主語や目的語につく助詞「を」の省略
(例)それには色々の魂の玉橋渡せり。
<訳>色々な玉でできた橋を渡してある。
「橋」のあとに「を」が省略されていた。
【3】並列や対の関係にある主語の省略
(例)足強気人は、早く、よわきは行くこともおそきも、よく似たり。
<訳>足が強い人は早く進み、弱い人は進むのが遅い点も、よく似ている。
「よわき」のあとに、「人」が省略。
主語の省略
古文では主語が省略されている場合が多い。登場人物を確認し、前後の内容から主語を捉えることが必要。
(原文)男あまたゐる。たいそうののしりあう。
(補った文)男があまたゐる。男はたいそうののしりあう。
(現代語訳)男がたくさんいる。男(たち)は、大騒ぎしている。
助詞の省略
古文では助詞が省略されている場合が多い。自然な文章になるように助詞を補って、文脈を捉える。
- 前の文と同じ主語なので省略されている。
- 文の途中で主語が変わることがある。
以上が、中学国語・古文「主語・助詞の省略の見抜き方」となります。
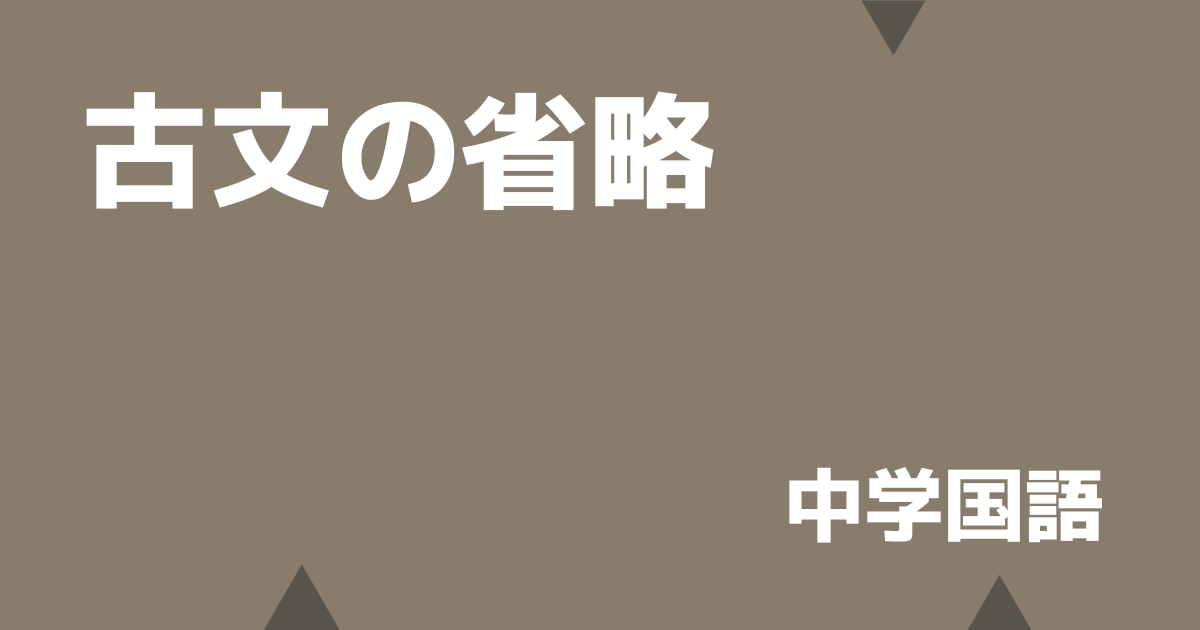

コメント