【中2国語】徒然草の定期テスト対策予想問題です。
徒然草の定期テスト対策予想問題
次の文を読んで、問いに答えなさい。
仁和寺にある法師、年寄るまで、石淸水を拝まざりければ、➊心うく覚えて、ある時思ひ立ちて、ただひとり、徒歩よりまうでけり。極樂寺・高良などを拝みて、かばかりと心得て帰りにけり。
さて、かたへの人にあひて、「➋年ごろ思ひつること、果たし侍りぬ。聞きしにも過ぎて、➌尊くこそおはしけれ。そも、参りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん、➍ゆかしかりしかど、神へ参るこそ本意なれと思ひて、山までは見ず」と言ひ( ➎ )。
➏少しのことにも、先達はあらまほしきことなり。
問一 下線部➊の意味として適切なものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア 残念に思って
イ 恐ろしく思って
ウ 不愉快に思って
エ 心うきたつ思いで
問二 下線部➋は具体的にはどのようなことでしたか。十字以内の現代語で書きなさい。
問三 下線部➌とありますが、この法師は何を見てこのように言っているのですか。文中から抜き出しなさい。
問四 下線部➍で、法師は何を知りたかったのですか。現代語で書きなさい。
問五 下線部➍のことを知りたかったのにもかかわらず、なぜ山に登らなかったのですか。その理由が書かれた部分を文中から抜き出しなさい。
問六 ( ➎ )は、係りの助詞「ぞ」がかかって文末の結び方が変わっている部分です。「けり」を適切な形に直して書きなさい。
問七 筆者が下線部➏と考えたのは、この法師の、どのようなことがきっかけになったからか。三十字以内の現代語で書きなさい。
徒然草の定期テスト対策予想問題の解答
問一 ア
問二 石清水の行きたいこと。
問三 極楽寺・高良
問四 参拝者がみんな山に登っていく理由う。
問五 神へ参るこそ本意なれと思いて、山までは見ず。
問六 ける
問七 (例)法師は石清水に参拝したかったのに、思い込みで行けなかったから。
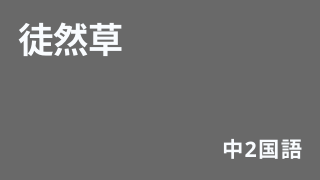

コメント