高校入試対策・国語の「詩の鑑賞」ポイントをまとめています。詩は、作者の受けた感動をリズムのある短い言葉で表したものです。言葉の意味や表現技法に注意して、解いていくことが必要となります。それでは、高校入試対策・国語「詩の鑑賞のポイントまとめ」です。
詩の鑑賞
<用語>
- 文語詩…文語(昔の言葉)で書かれた詩
- 口語詩…口語(現代の言葉)で書かれた詩
<形式>
- 定型詩…五七調や七五調など音数にきまりのある詩
- 自由詩…音数にきまりがない、自由な形の詩。
- 散文詩…散文(普通の文)のように書かれた詩
詩の構成の特色
- 行分け…詩は散文と異なり、文の途中でも行を超えることができます。
- 連…内容の一まとまりで、行を少しあけて書かれます。散文の段落にあたる。
おもな詩の表現技法
比喩法(たとえ)
- 直喩法…「ようだ」などを使い、2つのものを直接結びつけます。(例)りんごのよなほっぺ。
- 隠喩法…「ようだ」などを使わず、たとえます。
- 擬人法…人でないものを人に見立てて表現します。
その他の技法
- 倒置法…語順を逆にして、印象を強めます。(例)どうだろう この沢鳴りの音は
- 反復法…同じ語句を繰り返してその部分を強調します。
- 対句法…対になる語句を並べて印象を強めます。
- 体言止め…行末で体言で止めて余韻を弧越します。
詩の勉強
行と行、連と連の間の変化から心情の移り変わりをつかむことがコツです。作者が心情を表した部分、倒置法や反復法などで強調された部分にも注目します。
主題についてですが、作者の感動の中心となる連や部分の内容、詩の題目にも注目します。

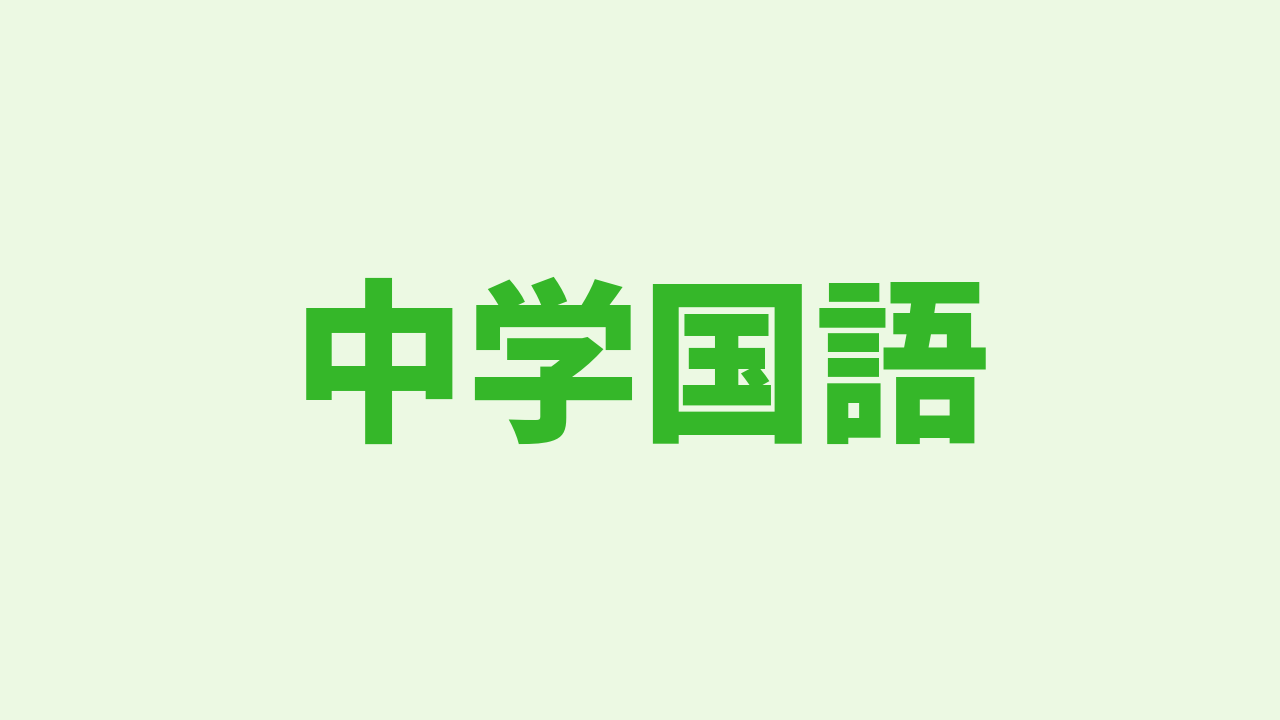

コメント