中学理科で習う実験一覧(よく出る覚えておくべき編)についてまとめています。「実験」に絡めて出題されることが多いのが、理科の高校入試の特徴です。中学理科で習うもののうち、よく出題されるものを振りかえってみましょう。
中1理科で習う実験一覧
光合成の実験
<手順>
- アサガオの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、光を十分にあてる。
- あたためたエタノールに入れて脱色する。
- 水洗いしたあと、ヨウ素益にひたす。
- 葉緑体にあたった部分が青紫に染まる。
- 光合成には、光と葉緑体が必要なことがわかります。
対照実験とは、比較のために調べようとすることがら以外の条件を同じにして行う実験のこと。
蒸散の実験
蒸散は、根から吸い上げられた水が、植物の体から水蒸気として放出される現象。このことによって、根からの水の吸収がさかんになります。蒸散による水蒸気の放出はおもに、気孔を通して起こります。大気中の酸素や二酸化炭素なども主に気孔を通して出入りをします。
<蒸散の実験>
- 油を塗ります。水面からの水の蒸発を防ぎます。
- ワセリンを塗ります。気孔をふさぎ、蒸散をさせません。
A そのまま水にさしたもの
B 葉の表にワセリンをぬる
C 葉の裏にワセリンをぬる
この場合、水の減り方が多いものから順に並べると、 A→B→Cとなります。
茎のつくりを調べる実験
<手順>
- 着色した水を三角フラスコに入れ、植物をさし、水を吸わせます。
- 着色した植物の茎を、輪切りにしたり、縦に切ったりして、顕微鏡で観察します。
<結果>
- 茎の内部で、着色した部分を着色しなかった部分がある。
- 茎の内部で、着色した部分の並び方にちがいがある。
<考察>
- 茎の内部には、吸収した水が通る管(道管)がある。
植物の呼吸を確かめる実験
<手順>
- 空気にふくまれている酸素と二酸化炭素の体積の割合を気体検知管で調べる。
- ボリエチレンの袋に植物を入れて口を閉じ、数時間暗いところにおく。
- 袋の中の酸素と二酸化炭素の体積の割合を気体検知管で調べる。また、袋の中の空気を石灰水の中に押し出してしらべる。
<結果>
- 気体検知管で調べる…酸素の体積の割合は減り、二酸化炭素の体積の割合は増える。
- 石灰水で調べる。…石灰水が白くにごる。
<考察>
- 植物は、光があたらないとき、酸素を取り入れて、二酸化炭素を出している。
アンモニアの噴水実験
<手順>
- スポイトのゴム球をおして、水をフラスコの中に入れる。
- 水が吸い上げられて、フラスコの中に赤色の噴水がみられる。
<考察>
- フェノールフタレイン液は、酸性や中性の水溶液では無色だが、アルカリ性の水溶液では赤色に変化する。
- アンモニアは水に非常に溶けやすい。
みりんを蒸留してエタノールを取り出す実験
<手順>
- 試験管にみりんをとり、弱火で加熱する。
- 3本の試験管アイウに液体を集める。
- 集めた液体を次のAからCのようにして調べる。
A…匂いを調べる
B…脱脂綿につけて、火をつける。
C…皮ふにをつける。
<結果>
- 試験管ア A(エタノールのにおい) B(長く燃える)C(冷たい感じがする)
- 試験管ウ A(においはしない)B(燃えない)C(ぬれて残る感じがする)
<考察>
- 加熱するとまずエタノールを多く含む気体が、次に水蒸気を多く含む気体が出てくる。
スポンジのへこみ方の違いを調べる(圧力の実験)
<手順>
- レンガの質量とAからCの場合のレンガの床面積を測る。
- レンガ置く向きを変えて、レンズのへこみ方を調べる。
<考察>
- 同じ大きさの力でも、力を受ける面積が小さいほど、スポンジのへこみ方を大きくなり、力の効果が大きくなります。
中2理科の実験一覧
酸化銀の熱分解の実験
- 酸化銀を加熱すると酸素が発生し試験管には銀が残る。
- 酸化銀は黒色、銀の白色をしている。
- 発生する気体を水上置換法で集めるのは、酸素が水に溶けにくいという性質をもつためです。
- 水が逆流しないようにガスバーナーの火を消す前にガラス管を水槽から出す。
炭酸水素ナトリウムの熱分解の実験
炭酸水素ナトリウムを加熱し次のことを調べる。
<調べること>
- 発生した気体を調べる。
- 加熱した試験管の口に生じた液体を調べる。
- 加熱前と加熱後の固体の性質を調べる。
<注意>
- 水が逆流しないように火を消す前にガラス管を水槽から出す。
- 生じた液体が加熱部分に流れないように試験管の口を少し下向きにする。
<結果>
- 石灰水が白く濁る。発生した気体は二酸化炭素。
- 青色の塩化コバルト紙が赤色に変わる。生じた液体は水。
- 炭酸水素ナトリウムは、水に溶けにくく、水溶液にフェノールフタレイン液を加えるとわずかに赤色になる。
- 加熱後の物体は、水によく溶け、水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えると、はっきりと赤色になる。→強いアルカリ性で加熱前と違う物質。
炭酸水素ナトリウムの熱分解は、加熱すると3種類の物質に分解する。
炭酸水素ナトリウム(固体)→炭酸ナトリウム(固体)+二酸化炭素水(気体)+水(液体)
水の電気分解の実験
- 純粋な水は電流をほとんど通さないので、水酸化ナトリウムを溶かし薄い水溶液とし、水に電流が通るようにする。
- 水酸化ナトリウムを溶かした水が目に入ったり、手にしたりした時には大量の水で洗い流す。
- H字形の電気分解装置の場合、管内に液体を入れる時には、ビッチコックを閉じておき、電気分解をしてる間はヒッチコックを開いておく。また、ゴム栓はずすときは、ビッチコック閉じる。
酸化銅を還元して銅を取り出す実験
<手順>
- 酸化銅と炭の粉末の混合物を加熱し、石灰水の様子を観察する
- 試験管に残った混合物の色を観察する。
<結果>
- 石灰水が白く濁る→発生した気体は二酸化炭素。
- 赤色でこすると光る。→酸化銅が銅に変わった
酸化銅と炭素の混合物を加熱する実験
<手順>
- 酸化銅と炭素を乳棒と乳鉢を使ってよく混ぜる
- 酸化銅と炭素の混合物を入れた試験管を加熱するときは、試験管の口を少しさげます。
- 反応が終わったら石灰水が逆流しないようにガラス管を石灰水からにきます。
- 空気調節ねじ、ガス調節ねじの順に、閉めてガスバーナーの火を消します。
- 空気が試験管の中に流れ込み、その中の酸素と銅が化合しないようにピンチコックを閉めます。
鉄と硫黄の混合物の加熱実験
鉄と硫黄の混合物を加熱するとどうなるかを調べる実験です。
<手順>
- 鉄と硫黄よく混ぜ、2本の試験管a,bに分けて入れる。
- 試験管bの混合物の上部を加熱する。
- 混合物の上部が赤くなったら加熱をやめる。
- 加熱前後の物質の性質を調べる。
・磁石を近づけてみる
・少量をとって塩酸に入れて、発生する気体のにおいを調べる。
| 磁石を近づけたとき | 塩酸を入れたとき | |
| 加熱前の混合物 | 引きつけられる | においのない気体(水素)が発生する |
| 加熱後の物質 | 引きつけられない | においのある気体(硫化水素)が発生する |
<結果>
鉄と硫黄の混合物を加熱すると化学変化が起こって別の物質が生成されることがわかる。
鉄と硫黄の混合物の加熱実験についてまとめると、
- 鉄と硫黄の混合物を加熱するときは、混合物の上部を加熱する。
- 混合物を加熱すると光と熱を出して、化学変化が起こる。
- いったん、化学変化が始まると加熱をやめても化学変化が進む。
- 非常に温度が高くなって危険なので赤くなり始めたら必ず加熱をやめること。
- 加熱によって別の物質に変化することは、磁石を近づけたり、物資を塩酸に入れたりすることを確かめられる。
| 加熱前の混合物 | 加熱後の物質 | |
| 磁石を近づける | (混合物の鉄が)引きつけられる。 | 引きつけられない。 |
| 塩酸に入れる | においのない気体(水素)が発生。 | ゆでたまごのようなにおいのある気体(硫化水素)が発生。 |
化学変化の前後と質量の実験
まずは、質量の保存に法則について、化学変化の前後と質量がどうなっているかの実験をみてみましょう。
<手順>
- 装置全体の質量測る
- 密閉した容器を傾けて二酸化炭素を発生させる
- 反応後の装置全体の質量をはかる。
<結果>
- 結果容器を密閉した状態では反応の前後で装置全体の質量は変わらない。
もう1つのやり方
<手順>
- 化学変化前の質量測る
- 水溶液を混ぜて水に溶けにくい炭酸カルシウムを生じさせる。
- 反応語の全体の質量をはかる。
<結果>
- 反応の前後で全体の質量は変わらない。
酸化銅の実験
銅と酸素が化合するときの質量の割合を調べたり、銅を加熱したときの質量の変化を調べる実験です。
<手順>
- 銅の質量を0.40g、0.80g …とはかり、皿に広げて、全体の色が変化するまでよく加熱する。
- 皿が冷めてから質量をはかる。
- 薬ざしで、こぼさないようによくかき混ぜる。
- 質量の変化がなくなるまで1~3まで繰り返した後、2の質量から皿の質量を引いて、生成した酸化銅の質量を求める。また化合した酸素の質量を求める。
化合した酸素の質量=酸化銅の質量-銅の質量
<結果>
| 銅(g) | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| 生成した酸化銅の質量(g) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 化合した酸素の質量(g) | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
<考察>
銅の質量と生成した酸化銅の質量及び銅の質量と化合した酸素の質量の関係をそれぞれグラフに表すとどちらも原点を通る直線になります。このことから次のことが言えます。
- 銅の質量と生成する酸化銅の質量は比例する。
- 銅の質量と化合する酸素の質量は比例する。
細胞のつくり
細胞のつくり植物と動物の細胞を観察する実験です。
<手順>
- タマネギのりん茎の内側に切り込みを入れ、表皮をはがし、スライドガラスにa,bに1枚ずつのせる。
- aに水を1滴落として、カバーガラスをかぶせる。
- bに染色液(酢酸カーミン液など)を落として、3分間ほどおき、カバーガラスをかぶせる。
- 2枚のスライドガラスにオオカナダモを葉を1枚ずつのせ、2,3と同様にプレートパレードをつくる。
- ほかの内側を綿棒でこすりとり、綿棒を2枚のスライドガラスにこすりつけ、2,3と同様にプレパラートをつくる。
- 顕微鏡で観察し、スケッチする。
テンプンに対するだ液のはたらきの実験
<手順>
- 試験管Aにはデンプン溶液とだ液、試験管Bにはデンプン溶液と水を入れて混ぜ合わせ、36℃くらいのの水に10分間入れておく。
- A,Bの液をそれぞれ2本に分け、一方はヨウ素液を加え、もう一方はベネジクト液を加えて熱し、それぞれの色の変化を見る。
<結果>
| ヨウ素液 | ベネジクト液 | |
| Aの液 | 変化なし | 赤褐色ににごる |
| Bの液 | 青紫色になる | 変化なし |
<考察>
だ液を入れた試験管だけで、ヨウ素液に反応せず、ベネジクト液に入れて加熱すると赤褐色ににごることから、デンプンが分解されたことがわかる。
落ちてくるものさしをつかむ実験
落ちてくるものさしをつかむ実験では、「目に光の光が入る→刺激は網膜の感覚細胞で信号に変えられて脳に伝える。→脳でその内容を理解し、どう反応するかが決定される。→脳から出た信号がせきずいを通って筋肉に伝わり運動が起こる。」の順に刺激が伝わります。
電熱線にかかる電圧を変えて電流の変化を調べる実験
<手順>
- 回路で、電熱線の両端にかかる電圧を1.0V、2.0V…5.0Vと変えて、そのときの電流をはかります。
- 別の電熱線にかえて、1と同じ操作を行います。
<結果>
| 電圧(V) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 電流(mA) | 最初の電熱線 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 別の電熱線 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
<考察>
- グラフを書くと、原点を通る直線となります。電熱線を流れる電流は電圧に比例します。
- 同じ電圧を加えた時、最初の電熱線は、別の電熱線より流れる電流が小さいです。最初の電熱線の方が電流が流れにくいということです。
露点をはかる実験
<手順>
- 気温をはかった後、金属製のコップの中にくみ置きの水を入れ、温度をはかる。
- 水温を下げ、コップの表面がくもり始めたときの温度を読む。
<結果>
- コップ表面のくもり始めたときの水の温度は、9.0℃であった。
<考察>
このときの水の温度は、コップの表面付近の空気の温度と同じだけと考えられるので、この空気の露点は9.0℃です。
雲のできるようすを調べる実験
<手順>
- 装置をつくり、ピストンをすばやく引き、フラスコの中のゴム風船のようすや温度の変化を観察します。
- フラスコの中の少量の水をぬらした後、線香の煙を入れ、ピストンを引いた入り、おしたりしてフラスコの中のようすを観察します。
<結果>
- ピストンを引くと、ゴム風船はふくらみ、温度が下がる。
- ピストンを引くと、温度が下がって、フラスコ内の白くくもる。
- ピストンをおすと、温度が上がって、フラスコ内の白いくもりが消える。
<考察>
- 気圧が低くなると、空気が膨張して、温度が下がる。
- 空気が膨張するとき、フラスコ内の空気が露点以下になち、水蒸気が水滴になって白くくもる。
- 気圧が高くなると、空気がおし縮められて温度が上がって、水蒸気にもどり見えなくなる。
中3理科の実験一覧
記録タイマーで速さを調べる実験
<手順>
- テープを手で引いて打点間隔がどのように変わるかを調べる。
「同じ速さで、ゆっくり引く」
「同じ速さで、早く引く」
「だんだん早く引く」 - テープを手にもって、できるたけ一定の速さになるように歩いて記録タイマーで記録する。
<結果>
- 「同じ速さで、ゆっくり引く」と「同じ速さで、早く引く」では、打点間隔は一定ですが、5打点(0.1秒)ごとの長さは、「同じ速さで、早く引く」の方が長いです。「だんだん早く引く」は、打点間隔はだんだん長くなります。
- できるたけ一定の速さで歩いたとき、5打点ごとのテープの長さは、ほぼ同じになる。
<考察>
- 運動が遅いときは打点の間隔がせまく、速いほど間隔が広がります。一定の速さの運動では、一定の間隔で打点されます。
斜面を下る台車の運動実験
<手順>
- 斜面に台車を置き、台車にはたらく斜面にそう力の大きさを、斜面上の3か所ではかります。
- 台車の斜面上での運動を記録タイマーで記録します。
- 斜面の角度を変えて、1,2と同様に実験します。
<結果>
| 場所A | 場所B | 場所C | |
| 角度5° | 0.8 | 0.78 | 0.79 |
| 角度10° | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
- 0.1秒(5打点または、6打点)ごとにテープを切って、左から順に下端をそろえて台紙に並べてはる。
<考察>
- 台車にはたらく斜面にそう下向きの力は、斜面のどこでも同じで、斜面が急なほど大きいです。
- 台車の速さはしだいに増加し、その増え方は斜面が急なほど大きいです。
真下に落下する物体の運動(自由落下運動)の実験
- 真下に落下する運動は、斜面の傾きが多くなって、90度になったときと考えることができます。
- 1のことから考えることができるように、斜面上の運動よりも下向きの力が大きくなるため、速さの増え方は、斜面上を運動させるより大きくなります。
- 空気抵抗を考えなければ、物体の落下する速さの変化のしかたは、物体の重さによって変わりません。
力がはたらかない運動実験
水平な台の上を運動する台車を調べます。
<手順>
記録タイマーのスイッチを入れ、台車を手のひらでポンとたたき、運動を記録タイマーで記録します。テープの記録をもとに次の1~4の処理を行います。
- テープ5打点(または6打点)ごとの台車の進んだ距離をはかり、表に記入する。
- テープ5打点(または6打点)ずつ切って、台車に並べてはる。
- 台車の速さと時間の関係をグラフにする。
- 台車の進んだ距離と時間の関係をグラフにします。
<結果>
| 打点(打) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 距離(cm) | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
- 時間と距離は比例し、時間が経っても速さは一定。
位置エネルギーの大きさを調べる実験
高さや質量の関係について調べます。
<手順>
- 質量のちがう2つの金属球A,Bのそれぞれについて高さを変えて転がし、木片にあてて、移動距離を測定します。
<考察>
- 木片の移動距離は、金属球が高いほど大きく、金属球の質量が大きいほど大きい。
運動エネルギーの大きさを調べる実験
速さや質量の関係について調べます。
<手順>
- 質量のちがう2つの金属球A,Bのそれぞれについて。速さを変えて運動させ、木片にあてて、移動距離を測定します。
<考察>
- 木片の移動距離は、金属球の速さが速いほど大きく、質量が大きいほど大きいです。
花粉の変化を調べる実験
- スライドがらすに10%の砂糖水を1滴落とし、筆を使って、その上にホウセンカやカボチャの花粉を落とします。このとき10%の砂糖水の上に落とすのは、めしべの柱頭と同じような状態を再現するためです。
- 5~10分後、花粉管がのびるようすを、顕微鏡を使って100~150倍で観察します。
メンデルが行った実験の結果
- 子では、すべての個体に両親の一方の形質が現れます。
- 孫では、子の両親の一方の形質が現れているものと、もう一方の形質が現れているものとがあります。
- 孫での形質の現れ方の比は3:1になっています。
以上が、「形質を伝えるものは、2つ集まって対になっています。両親のこの形質を伝えるものは2つに分かれて、その1つずつが子に伝えられ、子ができるときに新しい対ができる。」とかばえた。
- 対立形質…丸としわのように、どちらかしか現れない形質どうし。
土の中の菌類・細菌類のはたらきを調べる実験
Aのビーカーの液には、微生物がふくまれているので、デンプンが分解され、ヨウ素液を入れても変化しない。Bのビーカーの液には微生物がふくまれていないので、デンプンが分解されず、ヨウ素液を入れると青紫色になります。
<考察>
- 微生物のはたらきで、デンプンが分解されることがわかります。
電流をとりだす実験
いろいろな金属と食塩水で電流が取り出せるか調べる実験です。
<手順>
- 食塩水に銅板と亜鉛版を入れ回路を組み立てて、電子オルゴールが鳴るかどうか調べます。
- オルゴールの+と-を逆につなぎ、鳴るかどうかを調べます。
- 金属の組み合わせをかえて、オルゴールの鳴り方を調べます。
<結果>
| +極 | -極 | オルゴールの鳴り方 |
| 銅 | 亜鉛 | 曲とわかる遅く弱い |
| 銅 | マグネシウム | はっきりと曲が聞こえた |
| 亜鉛 | マグネシウム | 音はするが曲にはならない |
- 2で、つなぎ方を逆にすると鳴らない。
- 3で、銅板と銅板など、同じ種類の金属板を使うと鳴らない。
<考察>
食塩水に2種類の金属を入れると、電子オルゴールが鳴るので、電池になったとわかります。用いる金属がどちらの極になるかは、金属の組み合わせによって変わります。
中1理科の観察一覧
植物の呼吸の観察
<手順>
- 空気にふくまれている酸素と二酸化炭素の体積の割合を気体検知管で調べる。
- ボリエチレンの袋に植物を入れて口を閉じ、数時間暗いところにおく。
- 袋の中の酸素と二酸化炭素の体積の割合を気体検知管で調べる。また、袋の中の空気を石灰水の中に押し出してしらべる。
<結果>
- 気体検知管で調べる…酸素の体積の割合は減り、二酸化炭素の体積の割合は増える。
- 石灰水で調べる。…石灰水が白くにごる。
<考察>
植物は、光があたらないとき、酸素を取り入れて、二酸化炭素を出している。
シダ植物の観察
<手順>
- 全体を観察する
- シダ植物の葉は緑色をしています。
- 葉の裏に胞子のうがあります。
- 葉の裏の胞子のうを乾燥させ、ルーペ(または、双眼実体顕微鏡)で観察する。
- 小さくて丸い形をした胞子が飛び出す。
<考察>
- シダ植物は、葉で光合成する。
- 地面から出た部分は、全部葉で、茎は地中にあります。
安山岩と花こう岩の観察
鉱物の大きさや形、集まり方から、つくりの違いを調べる。
<考察>
安山岩は、大きい鉱物が、粒のよく見えない部分の中に散らばって見える。花こう岩は同じぐらいの大きさの鉱物がきっちりと合わさっている。
地面の揺れの観察
<手順>
地震が発生してから各地で揺れはじめるまでの時間を20秒ごとに色を変えてぬる。
<結果>
色分けした境目を線で結んでいる。
<考察>
- 地面の揺れは、水面に広がる波紋のように、震源から四方に向けてほぼ同じ速さで広がっていく。
- 地震が発生してから揺れは始めるまでの時間は、震央からの距離が遠い地点ほど長くなります。
地層の観察
地層のつながりは、いくつかの露頭の観察やボーリングで得られた試料をもとに地層でつないでいくことで推定できます。
- ボーリング…機械で大地に穴を掘って、地層の試料を取り出すこと。この方法で詐取した試料をボーリング試料といいます。
- 柱状図…1枚1枚の層の重なり方を柱状に表したもの。
- かぎ層…火山灰の層のような、地層の広がりを知る上で目印となる層。
中2理科の観察
細胞のつくりの観察
細胞のつくり植物と動物の細胞を観察する実験です。
<手順>
- タマネギのりん茎の内側に切り込みを入れ、表皮をはがし、スライドガラスにa,bに1枚ずつのせる。
- aに水を1滴落として、カバーガラスをかぶせる。
- bに染色液(酢酸カーミン液など)を落として、3分間ほどおき、カバーガラスをかぶせる。
- 2枚のスライドガラスにオオカナダモを葉を1枚ずつのせ、2,3と同様にプレートパレードをつくる。
- ほかの内側を綿棒でこすりとり、綿棒を2枚のスライドガラスにこすりつけ、2,3と同様にプレパラートをつくる。
- 顕微鏡で観察し、スケッチする。
ザリガニの体のつくりの観察
<手順>
- 体のつくりを観察する。
- 運動の様子を観察する。
- えさの取り方を観察する。
<結果>
- 節のある足を曲げたり伸ばしたりして運動する。
- 複雑な作りの口から食物をとる。
イカの体のつくりの観察
<手順>
- 体のつくりを観察する。
- あしの数や形、ひれや目などを観察する。
- 外とう膜を切り開いて観察する。
<結果>
足には節がない吸盤がある。
中3理科の観察一覧
体細胞分裂の観察
- 体に変化が始まる。
- 核の中に染色体が見えてくる。
- 染色体は太く短くなって縦に2つに割れる。
- 染色体は両方に同じように分かれる。
- 染色体がかたまりになり、植物は間にしきりが、動物はくびれができる。
- 新しい2つの細胞になる。
太陽の表面の観察
<手順>
- 太陽投影板をとりつけた天体望遠鏡で、黒点の位置と形を記録紙にスケッチします。1週間くらい継続して観察記録をとります。
- 望遠鏡で直接太陽を見てはいけません。フィインダーのキャップをつけておきます。
<結果>
- 黒点は東から西へ移動します。
- 黒点は中央部から周辺部へ移動すると、縦長に見えるようにします。
<考察>
- 太陽は地球からみて、東から西へ自転しています。
- 太陽は球形です。
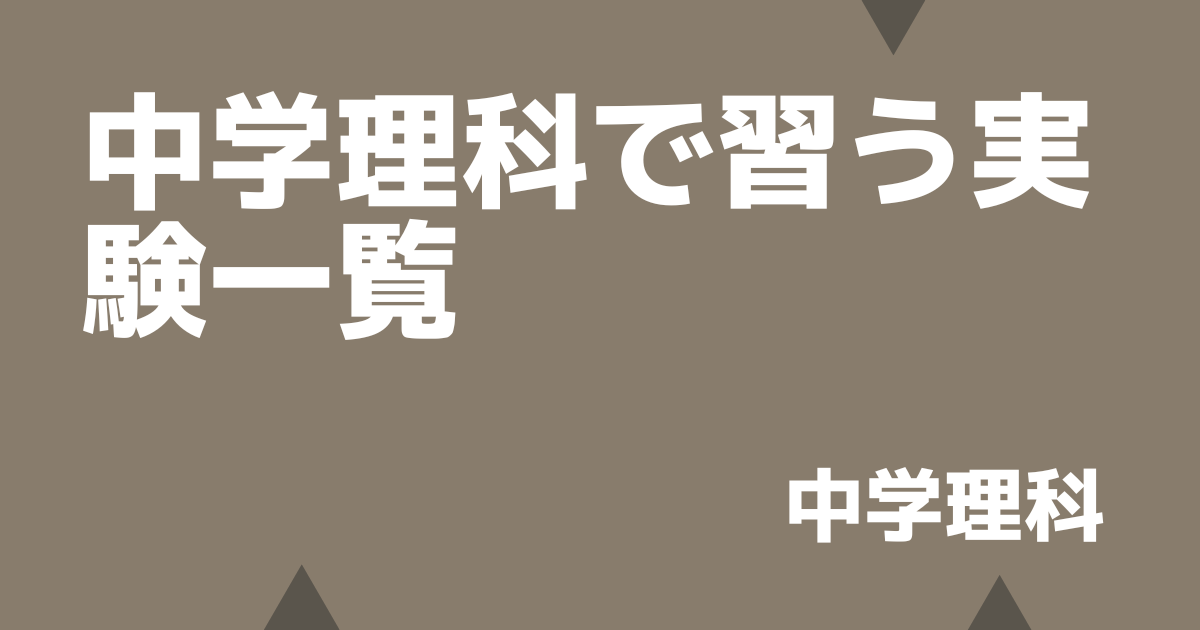

コメント