【中学社会】重要な法律一覧(高校入試・テストによく出る編)です。
重要な法律一覧
高校入試や実力テストでよく出る、覚えておきたい法律です。条約の名称、内容、成立時期などをセットで覚えていきましょう。
班田収授法
戸籍に登録された6歳以上のすべての人々に、性別や良賤(りょうせん)の身分に応じて、口分田をあたえ、死ぬと国に返されました。
墾田永年私財法
743年に、人々に開墾をすすめるために制定しました。貴族・寺院・郡司の私有地を広げ、私有地の事務所や倉庫は「荘」と呼ばれました。私有地が荘園と呼ばれるようになりました。
御成敗式目
1232年に北条泰時が御成敗式目を制定しています。執権政治を進めるための法律で、武士の慣習にも基づいて定められました。朝廷の律令とは別に独自に制定しました。長く武士の法律の手本となりました。
刀狩
農民や寺社から弓や刀、やり、鉄砲などの武器を取り上げれます。武力による農民の一揆を防ぎ、耕作に専念させました。自分の領地にいた武士は、大名の城下町に集められました。
武家諸法度
江戸時代初期の1615年に江戸幕府の2代将軍「徳川秀忠」が公布した基本法で、大名を統制するための法令。違反すれば、改易(領地没収)や減封(領地を減らされる)、転封(国替え、移封)などの処分が下されました。
キリスト教禁止令(禁教令)
キリスト教の教えが幕府の考えに反するためキリスト教禁止令(禁教令)を出しました。3代将軍家光は朱印船貿易を停止し、日本人の海外渡航と帰国を禁止しました。また、ポルトガル人を出島に移しました。
異国船打払令
外国船が接近し、外国船が日本に通商を求める。幕府はこれに対し、1825年に異国船打払令を出す。1842年に「薪水給与令」が発令されると廃止された。
王政復古の大号令
明治新政府の設立を宣言、天皇中心とする政治に戻すことを宣言。慶喜に官職と領地の返上を命じました。1867年に明治天皇により発せられた。
解放令
1871年に、えた身分、ひにん身分の呼び名を廃止し、これからは身分・職業ともに平民と同じにする法令。しかし、多くの面で差別が残った。
学制
小学校から大学までの学校制度。6歳以上の男女すべてに小学校教育を受けさせる。学校の建設費や授業料は地元で負担。当初は就学率が低かった。
徴兵令
1873年に、国民の兵役義務を定めた日本の法令。満二十歳に達した男子に兵役を義務付ける。免除規定はあった。
大日本帝国憲法
1889年2月11日天皇が国民与える形で発布。天皇が国の元首として統治すると定められ、帝国議会の召集、解散、軍隊の指揮、条約の締結、戦争を始めることなどが、天皇の権限として明記されました。
ワイマール憲法
1919年に公布されたドイツの憲法。国民主権、満20歳以上の男女が普通選挙権、労働者の団結権などを認めました。
普通選挙法
1925年、加藤高明内閣によって制定され、納税額による制限を廃止し、満25歳以上の男子選挙権を与えました。
治安維持法
普通選挙法と同時に制定。共産主義に対する取り締まりを強化。加藤内閣以後8年間、政党の総裁が内閣を組織。憲政の常道という。
国家総動員法
政府が産業・経済など全てにわたって戦争に動員する権限を持つ。
日本国憲法
1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行。
アイヌ文化振興法
1997年5月成立。 1899年の〈北海道旧土人保護法〉を廃止し、アイヌ民族の差別撤廃目指して。国会の「アイヌ民族を先住民とすることを求める決議」(2008年)など。
男女雇用機会均等法
1985年に成立した男女平等目指した法律。正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
男女共同参画社会基本法
1999年6月制定。男女が互いに人権を尊重しつつ,責任も分かち合い,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指す。
環境基本法
1993年に制定された日本の環境政策の基盤となる法律。環境保全のため、国や地方公共団体の責務を定めています。
情報公開法
国の官庁の持っている情報を、国民の要求に応じて公開すること定めた法律。
地方分権一括法
1999年に、地方公共団体が国の指示に従うのではなく、家の特徴に合わせて主体的に活動を行えるよう仕事や財政を地方に移すこと。
製造物責任法(PL)法
欠陥商品によって消費者が被害を受けた場合、消費者が企業の落ち度を証明しなくても損害を企業側に賠償させることができる。
消費者契約法
契約上のトラブルから消費者を保護する。
消費者基本法
消費者の権利を明確化し、企業と行政の責任を定める。消費者と事業者との間にある情報力や交渉力などの格差を是正し、消費者の利益を擁護、増進するため、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかすること。消費者の利益の擁護及び増進に関する消費者政策の推進を図ること。これらから、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的
種の保存法
1993年4月に施行された野生生物保護を目的とした法律で、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」である。ホ乳類や鳥類はもとより、それ以外の動物や植物まで、絶滅の恐れのある生物を保護するのが目的である。具体的には、次の内容がもりこまれ ている。
- 保存すべき種を保護し、譲渡などを禁じる。
- それらの生息地を保護区とし、土地の開墾や鉱石などの採掘、樹木の伐採などを制限する。
- 保護区において種の保存の必要性が認められたとき、その保護増殖事業を行う。
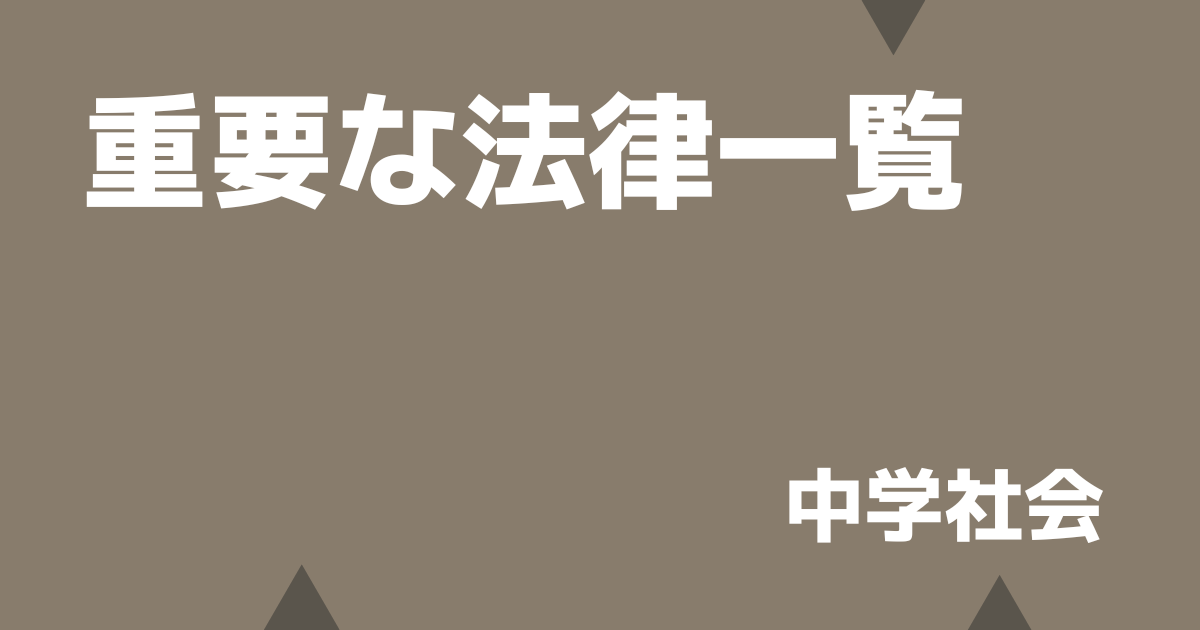
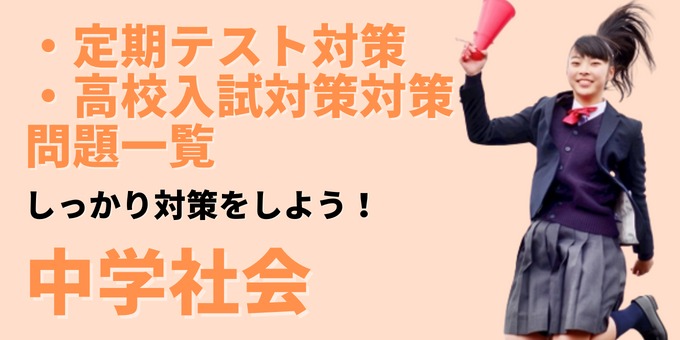
コメント