中学歴史「明治時代」についてまとめています。
明治時代の要点(ざっくり流れ)
明治維新(五箇条の御誓文1868年)
文明開化
明治維新の三大改革(学制:1872年・徴兵令:1873年・地租改正:1873年)
民選議院設立の建白書(1874年)
国会期成同盟の結成(1880年)
大日本帝国憲法発布(1889年)
日清戦争(1894年)
日露戦争(1904年)
条約改正(1894年・1911年)
明治新政府の成立
明治維新は、新政府の改革とそれに伴う社会の動きです。
- 五箇条の御誓文…天皇が出した新しい政治の基本方針
- 江戸を東京と改称し新しい首都にし、年号を慶応から明治にしました。
中央集権国家
藩から県へ中央集権国家を目指しました。
- 太政官…政治の権限を集中させる。
- 版籍奉還…藩に土地と人民を政府へ返させる。
- 廃藩置県…藩を廃止して県を置き、各県には県令(のちの県知事)を大阪、京都、東京の3府には府知事を中央から派遣。
- 藩閥政治…倒幕の中心であった公家、薩摩、長州、土佐、肥前の4藩出身者が実権を握る。
身分制度の廃止
- 四民平等…天皇一族の皇族以外、公家や大名の華族、武士の士族、百姓・町人の平民を平等とする。平民に苗字を認められ、住む場所や職業の制限もなくなる。「ちょんまげ」や帯刀が禁止される。
- 解放令…えた身分、ひにん身分の呼び名を廃止し、平民に。多くの面で差別が残る。
明治維新
富国強兵は、欧米に対抗するため、経済を発展させて国力をつけ軍隊を強化。学生、兵制、税制の三つの改革。近代化の基礎となる。
学制
小学校から大学までの学校制度。6歳以上の男女すべてに小学校教育を受けさせる。学校の建設費や授業料は地元で負担。当初は就学率が低かった。
徴兵令
満二十歳に達した男子に兵役を義務付ける。免除規定はあった。1873(明治6)年、富国強兵を目標とする政府は、近代的軍隊の設立のために徴兵令を公布した。国民皆兵が原則で、満20歳以上の成人男子に3年間の兵役を義務づけた。警察のしくみもととのえられ、1874年には東京に警視庁が設置された。
地租改正
土地に対する税率は全国統一の近代的な税となり、政府の歳入(年間の収入)の大半を占め財政を安定させた。年貢や大商人からの御用金にたよっていた政府の収入は不安定であった。これは、近代国家建設のための諸改革を行う障害となった。そこで、政府は収入を安定させるため地租改正を行った。
- 土地の所有者と価格地価を定め地券を発行する。
- 課税の基準を収穫高から地価に変更する。
- 税率は地価の3%で土地の所有者が現金を納める。
地租改正により、政府の収入は安定した。自作農は土地の所有権を認められ、売買も自由になった。いっぽう、小作農が地主におさめる小 作料は米などの現物で、その量は収穫高の30~50%にもなった。こうして農村の貧富の差は拡大し、各地で地租改正反対一揆が続発した。このため、政府は1877 (明治10)年に地租を2.5%に引き下げた。
近代的な国際関係
沖縄県の設置をします。琉球王国は、帰属を巡り清(中国)との対立。日本の領土として琉球藩を置きます。
- 台湾出兵…琉球の漁民が台湾の先住民に殺される事件が発生。台湾に出兵し、清から賠償金を得る。
- 琉球処分…軍隊の力を背景に沖縄県を設置。
清と朝鮮国との関係
- 清…対等な立場の日清修好条規を結ぶ。
- 朝鮮国…武力で開国を迫る。征韓論が高まりますが、岩倉具視や大久保利通らが反対。西郷隆盛、板垣退助らが政府を去る。(明治六年の政変)。軍艦を派遣して、江華島事件を引き起こし、日本に有利な不平等条約の日朝修好条規を結んで開国させます。
欧米との関係
- ロシアと樺太千島交換条約を結ぶ。
- 小笠原諸島の領有を各国に通告する。
- 近代化を欧米諸国に認めさせるため、欧米化政策をすすめ、法律の整備に力を注ぎました。
文明開化
文明開化は、欧米の文化が取り入れられ、都市を中心として伝統的な生活が変化し始めたこと。
進む世界の一体化で、資本主義が発展し、イギリス、ドイツ、アメリカ、ロシア、フランスなど経済力などを背景に世界に進出。また、蒸気船や鉄道の発達で人や商品の動き、情報の伝達が活発化なる。北アメリカと東アジアを結ぶ太平洋横断航路の開設、アメリカで大陸横断鉄道の完成、地中海とインド洋を結ぶスエズ運河開通など世界を一周する交通ルートができる。
- 神戸・横浜など開港地から新しい文化が広がる。
- 役所・学校などで、レンガ造りの欧米風の建物が増える。
- 道路には人力車・馬車が走り、ランプやガス灯がつけられる。
- 洋服やコート、帽子が流行し、牛肉を食べることが広がる。
- 太陽暦が採用され、1日24時間、1週間を7日となる。
新しい思想
近代思想を紹介したのが、福沢諭吉の「学問のすすめ」(人間の平等と民主主義)、中江兆民によるルソーの思想の紹介。自由民権運動とつながる。キリスト教の禁止が解かれ、信仰の自由が認められる。
日刊新聞や雑誌の発行で、新しい思想が広まる上で大きな役割を果たす。福沢諭吉の慶應義塾に、新島襄の同志社など私立学校の設立。
岩倉使節団
右大臣の岩倉具視を全権大使とする岩倉使節団を欧米に派遣。木戸孝允・大久保利通など政府の有力者のほぼ半数が参加。
目的は、不平等条約の改正でしたが、近代的な法制度が整っていないなどの理由で不成功に終わる。2年近くにわたって欧米の進んだ政治や産業、社会の情勢を体験する。帰国後日本の近代化を推し進める。
殖産興業と日本の関心
殖産興業は、近代的な産業を育てる政策。鉄道の開通や蒸気船の運行などの交通の整備。郵便制度や電子網の整備・富岡製糸場などの官営模範工場の建設。万国博覧会の参加(ジャポニズム)。
自由民権運動
板垣退助らは大久保利通らと政策を専制政治であると批判。国民が政治に参加できる道を開くべきだと主張し、民撰議員院設立の建白書を提出し国会の開設を求めました。板垣退助は、高知で立志社を結成し、運動を進めました。
士族の反乱
各地で、新政府に不満を持つ士族が武力蜂起。鹿児島の士族らが、西郷隆盛を中心に西南戦争をおこす。徴兵制で集められた政府軍に鎮圧される。藩閥政治への批判は、言論によるものが中心となる。
自由民権運動の高まり
自由民権運動は、国民が政治に参加する権利の確立を目指しました。西南戦争後、言論による政府批判が強まります。大阪で全国の代表が集まって、国会期成同盟を形成し、国会の開設を求めました。多くの憲法草案が民間で作成され、植木枝盛や中江兆民はフランスの人権思想を紹介しました。
政党の結成
大隈重信は、憲法の即時制定と国会の早期開設を主張しました。開拓者の施設や財産の払い下げをめぐる事件で民権派は政府を攻撃。伊藤博文は10年後に国会を開くこと約束。(国会開設の勅諭)。大隈重信を政府から追い出します。
国会開設に備え、板垣退助が自由党を、大隈重信が立憲改進党を結成。
立憲制国家の成立
憲法の準備が行われます。政府の弾圧と秩父事件などの民権派が関係した激化事件により自由民権運動は停滞。
- 伊藤博文…ヨーロッパに留学し、君主権の強いドイツ(プロセイン)などの憲法を学ぶ。帰国後に草案を作成。立憲政治(憲法に基づく政治)の開始に備え、内閣制度作り、伊藤博文が初代の内閣総理大臣(首相)に就任。
大日本帝国憲法
大日本帝国憲法は、1889年2月11日天皇が国民与える形で発布。天皇が国の元首として統治すると定められ、帝国議会の召集、解散、軍隊の指揮、条約の締結、戦争を始めることなどが、天皇の権限として明記されました。教育勅語は、忠君愛国(ちゅうくんあいこく)の道徳が示され、教育の柱になり、国民の精神的・道徳的なよりどころとされた。
- 性格…天皇が国民にあたえる憲法(欽定憲法)として制定されました。
- 元首…天皇が国の元首として日本を統治するとされました。
- 議会…貴族院と国民が選挙した議員からなる衆議院の二院制。さまざまな制限がありました。
- 国民…「臣民」と制定された。議会で定める法律の範囲内で、言論・出版・集会・結社・信仰の自由のなどの権限が与えられた。
- 民法や商法が公布され、法制度が整備された。
天皇の権限(天皇大権)
- 帝国議会の召集・解散
- 軍隊の指揮(統帥権)
- 条約の締結や戦争を始めること(宣戦)など
内閣の役割
天皇の政治を助けることが役割であり、各大臣は天皇に対して個々に責任を負うとされたため、議会に対する責任は不明確でした。
- 議会…貴族院と衆議院の二院制がとられました。
- 国民の権利…国民は「食」とされ、法律の範囲内で、言論、出版、集会、結社、信仰の自由などの権利が認められました。また、完全ではないものの、議会を通した国政参加の道が開かれました。
帝国議会
- 貴族院…皇族・華族、天皇から任命された勅選議員などで構成されました。
- 衆議院…選挙で選ばれた議員で構成されましたが、選挙権・被選挙権とも男性のみにあたえられ、納税額による制限もありました。
- 内閣と議会…予算や法律の成立に議会の同意が必要だったため、内閣は議会の協力が必要でした。
- 衆議院議員の選挙権を与えられたのは、直接国税を15円以上納める満25歳以上の男子のみ。人口の1.1%(約45万人)だった。
- 第1回衆議院議員選挙の結果、自由民権運動の流れをくむ野党(民党)が多数を占める。
- 議会制度が始まり、日本はアジアで最初の近代的な立憲制国家となった。
国家体制の整備
- 法制度の整備…刑法、民法、商法などの法律が制定されました。
- 教育勅語…1890年, 教育勅語が出され, 忠君愛国の道徳が示されました。教育勅語は教育の柱として、国民の精神的、道徳的なよりどころとして、日本社会のあり方に大きな影響をおよぼしました。
北海道の開拓とアイヌの人々
蝦夷地を北海道と改め、開拓使を置き統治を強化し、開拓事業。
- 屯田兵…農業兼業の兵士で開拓の中心となる。労働力不足は囚人やアイヌの人々で補う。困難な労働で多くの犠牲者を出しました。
- アイヌの人々…土地や漁場を奪われます。民族の伝統的な風習を禁止する同化政策により、民族固有の生活や文化の維持が困難になりました。
明治文化
アメリカ人のフェノノサが岡倉天心とともに、日本の美術の復興に努める。また、日本画の横山大観(無我)、狩野芳崖、彫刻の高村光雲が近代的な日本の美術を切り開きました、
黒田清輝が印象派の画風を紹介し、「湖畔」などを描きました。荻原守衛は欧米の近代的な彫刻を制作。滝廉太郎が「荒城の月」や「花」を作曲。
新しい文学
- 言文一致…文語の表現にかわって、話すように文章を書く。二葉亭四迷が小説で使用。
- 日清戦争前後…個性を重んじるロマン主義が主流。与謝野晶子、樋口一葉(たけくらべ)、島崎藤村など。
- 日ロ戦争前後…社会の現実を直視する自然主義が主流。その一方で、夏目漱石(坊ちゃん)、森鴎外が知識人の姿をえがいた小説を発表。
学校教育の普及
- 教育の普及…1907年に義務教育を6年に延長。小学校就学率は97%に達する。中等、高等教育の拡充。女子教育の重視。
- 科学の発展…北里柴三郎、野口英世など日本人による最先端の世界的な研究が登場しました。
帝国議会の成立
1890(明治23)年に行われた第1回衆議院議員選挙(総選挙)で選挙権があたえられたのは、地租などの直接国税を15円(年間)以上納める満25歳以上の男子で、全人口の1.1%にすぎなかった。
第1回帝国議会(国会)
1890年11月に開かれた。総選挙の結果、自由民権運動を指導した自由党や立憲改進党など民党(野党)の議員が過半数を占めた。そのため、軍備拡張問題や地租軽減などをめぐって藩閥政府(内閣)と民党は、するどく対立した。
1892年の第2回総選挙では、政府は、民党の進出をおさえるため、警官や暴力団などを使い選挙活動を妨害した(選挙干渉)。しかし選挙の結果、またも民党が勝ち、藩閥政府を苦しめた。
- 藩閥政治…倒幕の中心であった公家、薩摩、長州、土佐、肥前の4藩出身者が実権を握る。
政党政治の発達の理由
- 日清戦争(1894年)がおこると政府と民党が協力して戦争を進めたため、両者の対立が弱まったこと。
- 産業革命が進むにつれて力をつけた 資本家や地主が政党を支持したこと。
隈板内閣の成立
1898(明治31)年、自由党と進歩党(もとの立憲改進党)が合同して憲政党を結成した。これをもとに、首相に大隈重信、内務大臣に板垣退助が就任し、形式的には日本初の政党内閣がつくられた。
伊藤博文は、1900(明治33)年に立憲政友会をつくり、議会で多数を占め内閣を組織した。
殖産興業
殖産興業とは、明治新政府が欧米諸国の進んだ経済制度・設備・機械・技術などを取り入れて、近代産業の保護・育成をはかった政策である。新政府の成立当初は、まだ工場制手工業(マニュファクチュア)の段階で、民間には大規模な近代工業をおこす力がなかった。
- 工場制手工業(マニュファクチュア)…一部の問屋商人や大地主は、労働者を作業場に集め、道具を使って分業と協業で生産するしくみをつくりだした。
官営工場の設立
政府は欧米の先進国に追いつこうとして、外国から機械を買い入れ、外国人技術者を招き、重要鉱山を直接経営するとともに、官営の製糸・紡績工場や軍事工場などの官営工場を設立して、近代工業の育成をはかった。
1872年に開設された富岡製糸場(群馬県)はフランス人技師の指導のもとで、士族(旧武士)の子女を集めて大規模な生糸の生産を行った。ここで技術を習得した工女(女子労働者)たちは、各地につくられた民間の製糸工場で技術を指導する役割をはたした。
政府は1877年8月~11月に、上野公園(東京都台東区)内で第1回内国勧業博覧会を開き、新しい技術の紹介や普及をはかり、民間の産業の発達に大きな刺激をあたえた。
貨幣制度や金融機関の整備
江戸時代の藩札や明治の初めに発行された太政官札などが流通し、通貨は混乱していた。そこで政府は、1871年、円・銭・厘の10進法による新しい貨幣制度をつくった。
1872年には、殖産興業をおし進める資金を得ることや、不換紙幣(金・銀などの正貨と交換できない)の整理を目的に金融制度整備し、渋沢栄一らの意見を取り入れて 行銀行条例を定めた。
これにもとづいて、第一国立銀行をはじめとする民間経営の国立銀行がつくられた。これらの国立銀行は、1882年に日本銀行が開業して銀行券の発行業務をまかされると、1899年までに普通銀行となった。
明治時代の通信
1871年に郵便制度がつくられ、1872年には鉄道が開通した。政府は通信機関の整備をはかり、1869年、東京・横浜間に最初の電信を開通させた。1871年には長崎と上海(中国)の間に海底電線が開通し、海外との電信も可能になった。こうして、1880年代初めまでに全国の電信網がほぼ完成し、1849年には東京・横浜間で電話交換の業務も始まった。
1871年には前島密の努力で、これまでの飛脚がに代わってつくられた。郵便はまず、東京・京都・大阪で始められたが、1873年には全国均一料金で手紙・はがきが出せるようになり、全国の主要な郵便網がほぼ完成した。1877年には、万国郵便連合に加盟した。
明治時代の交通
交通の面でも整備がはかられ、1872年新橋 (東京都)・横浜間に初めて鉄道が開通し、1874年に大阪・神戸間、1877年に大阪・京都間が開通した。1889年には東海道線(東京・神戸間, 全長約590km)が全通した。海運業の発達もめざましく、沿岸航路で汽船の運航が行われるようになり、物資の輸送が活発になった。
韓国の植民地化
日本は韓国を保護国として、外交権を奪いました、韓国総督府を置き、伊藤博文が初代統監になりました。
- 義兵運動…皇帝が退位させられ、軍隊も解散。韓国国内に日本の支配に対する抵抗運動が広がり、解散させられた武士と農民がたちあがりましたが、日本軍が鎮圧。
- 韓国併合…日本は韓国を併合して、植民地とし、韓国総督府を設置。首都の漢城(ソウル)を京城と改称。学校では、朝鮮の文化や歴史を教えることを禁じ、日本史や日本語を教えて、日本人に同化させる教育を行いました。
- 皇民化教育…朝鮮の歴史を教えることを禁じ、日本史や日本語を教え、日本人に同化させる教育を行いました。
- 土地調査事業…土地制度の近代化を名目に土地調査事業を行い、土地の所有権が明確でないとして農民から土地をうばいました。
南満州鉄道株式会社は、満州での鉄道利権をもとに日本が設立しました。鉄道、鉄鋼の開発、製鐵所の建設など。満州への進出の機会をうかがっていたアメリカと対立。
中華民国の成立
- 孫文…三民主義を唱え、民族の独立と近代国家建設を目指す革命運動の中心となりました。
- 辛亥革命…長江上流域で民衆の反政府運動が起こる。武漢で軍隊が反乱起こし、革命運動は全国に広がり、多くの省が清から独立を宣言。孫文を臨時大統領として初めて最初の共和国である中華民国が建設される。首都は南京。
- 清の実力者の袁世凱が孫文と手を結び、清の皇帝を退位させ、清が滅びました。大統領になると独裁的な政治を行いましたが、袁世凱が死後、各地の軍閥がばらばらに支配するようになりました。
産業革命の進展
産業の発展では、軽工業の発展があり、1880年代後半から紡績業、製糸業などが発達。産業革命が始まりました。
- 紡績業…大工場と最新式の機械。国産の綿糸が輸入品を上回りました。
- 製糸業…生糸はアメリカ向けの輸出産業として発展。
- 動力源…筑豊地域(福岡県)や北海道の石炭での採掘。
- 重化学工業…日清戦争の賠償金をもとに北九州の官営八幡製鐵所の建設。
産業の発展とともに重化学工業製品の輸入が増加。輸出を上回りました。
- 東海道線が全線開通し、民営鉄道も発展しました。軍事上の必要性から民営鉄道が国有化されます。
- 海運業での海外航路の発展がありました。
資本家と労働者
- 女子労働者(工女)…紡績・製糸業の労働者の大半がそうでした。
- 男子労働者…多くは、鉱業や運送業で働いていました、
- 労働問題…労働組合が、形成され、労働条件の改善を求めました、労働争議が増加。
- 工場法の制定…12歳未満の就業禁止。労働時間の権限など定めました。
- 三井・三菱・住友・安田などの資本家が金融・貿易・工業などの多角経営で成長。日本経済を支配する財閥となりました、
- 公害問題…足尾銅山(栃木県)から輸出すると鉱毒によって、足尾銅山鉱毒事件が発生。渡良瀬川流域に大きな被害を及ぼしました、衆議院議員の田中正造が銅山の操業停止や被害者経済を求める運動を勧めました。
このころ、日本初の社会主義政党である社会民主党が形成され、天皇の暗殺を計画をしっとして、幸徳秋水ら12名の社会主義者が処刑される大逆事件が起こる。
地主と小作人
- 農村の変化…農作物の商品化が進み、輸入の影響でわた、麻、アブラナなどの栽培が衰えました。
- 製糸業…発展とともに、桑の栽培や養蚕が盛んになる。
- 零細農民や農地を持たない小作人は、子どもを工場に働きに出したり、副業を営んだりして生活。
- 農地を買い集めて経済力をつけた地主は、株式投資など資本主義との結びつきを強めた。
日清戦争
- 甲午農民戦争…東学(民間信仰をもとにした朝鮮の宗教)を信仰する人々を中心とする農民が朝鮮戦闘南部一体で蜂起。政治改革や外国人の排除を目指しました。
- 朝鮮の政府が清に出兵を求めたことをきっかけに日本も出兵。日清戦争が始まり日本が勝利する。
下関条約

日清戦争の講和条約
- 清は、朝鮮の独立を認め、遼東半島・台湾・澎湖諸島を日本に譲り渡す。
- 2億両(テール:当時の約3.1億円)の賠償金を日本に支払います。
台湾を統治した日本は、台湾総督府を設置して。植民地化を進める。
- 朝鮮…大韓帝国(韓国)と改め、清から独立を宣言。
- 中国分割…列強は競って、清に進出。
三国干渉
三国干渉は、ロシアがドイツ、フランスと共に、日本に遼東半島の清への返還を勧告し、日本はこれを受けいれて返還。ロシアは、日本が返還した地域の旅順と大連を租借して、根拠地としました、
清から得た賠償金で、軍事の拡張と工業化を進める。日本の重化学工業張の発展の基礎を気づいた官営の八幡製鉄所も、建設された。伊藤博文は、政治を安定させるため、1900年に立憲政友会を結成。以後、政党の中心となる。
日露戦争
義和団事件は、清で義和団を中心として外国の勢力排除しようとする事件。日本などの連合国が鎮圧しました。事件後。ロシア満州を占領後、韓国への進出。日本とイギリスは、日英同盟を結んでロシアに対抗。
日本国内に主戦論が高まりますが、幸徳秋水(社会主義者)や内村鑑三(キリスト教徒)などは反戦論を唱えました、また、与謝野晶子は、歌人の立場で主戦論に疑問を投げかけ、「君死にたまふことなかれ」という詩を発表しました。
日露戦争は、日本は苦戦しますが日本海海戦などで勝利。戦力が限界に達し、ロシアも国内で革命が起こり、両国とも戦争の継続が困難になりました、
ポーツマス条約

アメリカの仲介により講和条約を結ぶ。
ロシア日本に対し
- 韓国での日本の優先権を認める。
- 旅順、大連の租借権と長春以南の鉄道の利権を譲り渡す。
- 北緯50度以南の樺太(サハリン)に割譲する。
- 沿海州、カムチャッカ半島沿岸の日本の漁業権を認める。
日比谷焼き討ち事件
ポーツマス条約では、賠償金が得られず、日本の得た権限が少なかったため、国民は政府を攻撃します。東京で暴動を伴う民主の運動である日比谷焼き討ち事件が発生します、戦争のための重税、軍備の拡張で国民の負担が重くなりました、
日本は、列強都市の国際的な地位を固めます。アジア諸国に対する優越感が強まりました、アジア諸国は、近代化や民族独立の動きが高まり、中国では、革命運動が活発化しました。
欧米列強の侵略

列強と帝国主義が盛んになり、欧米で資本主義が急速に発展。資本家が経済を支配。列強は、イギリス・ドイツ・アメリカ・フランス・ロシアであり、帝国主義をとり、列強の国々は、資源た市場を求めてアジアやアフリカに進出。軍事力によって植民地化。
条約改正の達成
イギリスは、日本が大日本帝国憲法を発布し、帝国議会を開き、東アジアで国力を増してくると、日本の国際的な地位を重要視するようになってきた。
ロシアの南下にそなえて、日本と接近をはかる必要を感じていた。その結果、日清戦争直前の1894年、外務大臣陸奥宗光がイギリスと日英通商航海条約を結んで、領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部の回復に成功した。
日露戦争後の1911年には、外務大臣小村寿太郎がアメリカ合衆国と日米通商航海条約を結び、関税自主権を回復した。政府は、通商条約を結んでいた他の国々とも同様の条約を結び、不平等条約の改正を完全に達成した。
<その他の外国との事件>
- ラクスマン来航(1792)年…ロシア使節ラクスマンが根室に来航し通商を要求。幕府は拒否。
- レザノフ来航(1804)年…ロシア使節レザノフが長崎に来航し通商を要求。幕府は拒否。
- フェートン号事件(1808)年…イギリスのフェートン号が長崎に侵入し、オランダ商館から食料などを奪う事件
- モリソン号事件(1837)年…日本人漂流者を乗せたアメリカ商船モリソン号が浦賀に来航した。非武装だったが、幕府は異国船打払令により砲撃。山川でも砲撃。
<条約改正の実現までの過程>
- ノルマントン号事件…イギリス船が沈没し、日本人乗客が全員水死。イギリス領事裁判所は船長に軽い罰を与えただけだったので、不平等条約改正を求める世論が高まる。
- 条約改正…最初の応じたのは、アメリカで、1878年に関税自主権の回復に合意。しかしながら、イギリスなどの反対にあい実現せず。
- 鹿鳴館で舞踏会など開くなどの欧化政策。外国人判事を採用しますが、国内で反対を受けて失敗。
- 大日本帝国憲法の制定で、イギリスの交渉も応じる。
- 1894年外務大臣外相の陸奥宗光は、イギリスと領事裁判権を撤廃した日英通商航海条約を結ぶ。ほかの諸国とも改正が実現。1911年小村寿太郎外相が関税自主権の完全の回復に成功。
東アジアの情勢
- 朝鮮…日本と清が勢力を繰り広げ、朝鮮国内で親日派と親中派が対立。
- 甲申政変…親日はが日本と結んで実権握ろうとしますが、清に敗れる。
- 清に対抗するため日本は軍事の増強を図り、朝鮮への進出を首長。
琉球王国
江戸時代、琉球王国は日本と中国(清)の両方に属している(両属)関係にありました。
- 日本との関係…薩摩藩に事実上支配されていました。
- 中国との関係…清に朝貢し、清を宗主国としていました。
琉球処分
政府は琉球の両属関係を解消して日本に統合しようとしました。
- 清の対応…清は琉球王国の存続を主張し、琉球王国内の意見も、多くは両属関係を続けることを望むものでした。
- 琉球藩設置…1872年、政府は琉球国王尚泰(1843~1901)を琉球藩王に任じ、琉球藩を置きました。
- 琉球の漁民殺害事件…政府は、台湾で起きた琉球の漁民殺害事件を理由に台湾に出兵し、清から賠償金を得ました。
- 賠償金の支払い…賠償金には、相手国と国民に被害をあたえたことへの謝罪という意味があります。つまり、清は琉球の漁民を日本国民として認めたということになるのです。
1879年、政府は軍隊を送って土域(首里城)を占領し、琉球藩を廃して沖縄県を設置しました。
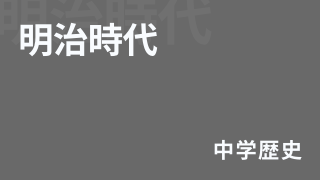
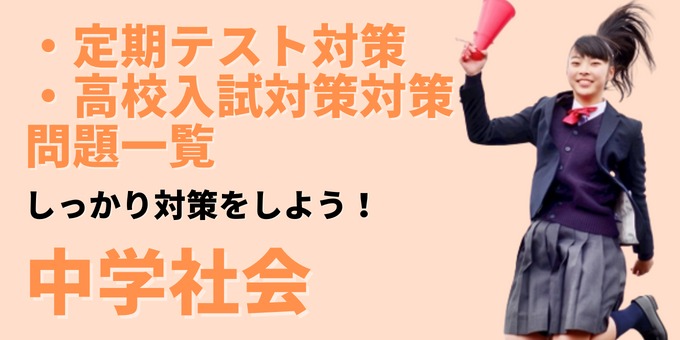
コメント