【中学歴史】戦国・安土桃山時代の要点まとめです。
戦国時代の要点
戦国大名の誕生
将軍は、京都を中心とするわずかな地方のみを支配。
- 下剋上…実力あるものが、力のばして上の身分の者に打ち勝って、下剋上の風潮が広がりました。
- 戦国大名…守護大名の地位をうばって実権をにぎった者、守護大名が成長した者が各地に登場。
応仁の乱以降を、戦国時代といいます。
分国法
戦国大名は、領国内の国人を従え、地侍などを家臣に取り立て、かれらの地位や収入を保障し、勢力を広げていった。また、家臣団と農民を統制して領国の支配を固めるために、分国法(家法)を制定した。この分国法は、家臣団の統制や農民の生活にかかわる規定、訴訟にかかわる規定などを主要な内容としていて、領国内の平和を保つために、違反者はきびしく罰せられた。
戦国大名の商業
さらに戦国大名は富国強兵策をとり、検地(田畑の調査) を行い、用水路や堤防を築いて農業をさかんにし、鉱山の開発にも努めた。城を中心につくった城下町には、家臣や商工業者を集め、商工業を保護した。
城下町
戦国大名が領国(りょうごく)につくったのが、城下町です。
- 城…山に築いていた城を、交通の便のよい平地に築きました。城の周辺に家来を集め、商工業者を呼び寄せ、城下町をつくりました。
- 分国法…鎖国を統一して支配するため、独自の法を定めました。
用水路の建設、鉱山の開発。交通路の整備、座の廃止。
自治都市
都市が発達して自治組織がつくられます。日明貿易や日朝貿易で栄えた博多(福岡県)や堺(大阪府)、応仁の乱から復興した京都などの都市では、寄合による都市の政治が行われます。
- 京都…自治をになう町衆と呼ばれる裕福な商工業者によって、祇園祭が行われました。
石見銀山(島根県)では、戦国大名の保護のもと博多の商人が開発。精錬(せいれん)技術の改良で生産量が増加し、海外に輸出しました。精錬(せいれん)技術は佐渡便残(新潟県)などにも、もたらしました。
安土桃山時代の要点
織田信長・豊臣秀吉の事業、貿易、桃山文化にふれています。
日本でのキリスト教の広まり
キリスト教は、大名から民衆まで広まっていきます。やがて、貿易の利益に着目しキリスト教を保護する大名も現れます。キリスト教を信仰する人(キリシタン)は増えていき、キリスト教徒となる戦国大名もあらわれました。
キリシタン大名
キリスト教に改宗した戦国大名です。南蛮船はキリスト教の布教を認めた港に来航したことから、南蛮貿易の利益を得ようとして改宗した大名が出てきました。九州にキリシタン大名 が多いのは、こうした背景があります。
- 大友宗麟(1530~87)…豊後(大分県)の戦国大名
- 大村純忠(1533~87)…肥前(長崎県)の戦国大名、長崎を教会に寄進。
- 有馬晴信(1567?~1612)…肥前の戦国大名
布教活動とキリスト教の広まり
宣教師たちの活発な布教活動によってキリスト教は広まりました。
- 宣教師の活動…宣教師は、九州(長崎・豊後など)や京都に教会、学校、病院、孤児院などを建設し、布教や慈善事業を行いました。
- 信仰の広がり…信仰は民衆にも広がり、17世紀のはじめには信者は 30万人を超えました。
織田信長の政策
- 桶狭間の戦い…愛知県で今川義元を破る。
- 足利義昭(あしあがよしあき)を援助して、京都にのぼります。その後、義昭を追放して、室町幕府を滅ぼします。
- 長篠の戦い…愛知県で1575年、鉄砲を有効に使った戦いで武田勝頼(たけだかつより)を破ります。
- 安土城(滋賀県)を築き、城下で楽市・楽座の政策。座や各地で関所(せきしょ)を廃止しました。
- 自治都市(堺)や仏教勢力(延暦寺、一向一揆)をきびしい態度で屈服させます。
- キリスト教の宣教師を優遇。
- 明智道秀にそむかれて、本能寺で自害。
豊臣秀吉の政策
豊臣秀吉は、検地・刀狩を行い、兵農分離(武士と農民の身分の区別を明確化し近世社会の基礎を作りました。
検地
田の広さや土地のよしあし、予想される生産量を調べることを検地といいます。豊臣秀吉は全国で検地を実施し、検地帳に記録させました。秀吉が行った検地を特に太閤検地といいます。
- ものさしやますの統一…土地の面積、生産量をはかる統一的な基準を定めました。全国で検地をするためには欠かせませんでした。
- 検地帳…検地帳には①田畑の面積②土地のよしあし(予想される生産量を石高であらわす) ③耕作し、所有する農民の名前(年貢を負担する者)が記入されています。
太閤検地には次のような意義があります。
- 統一的な基準…全国の土地が統一的な基準(石高)であらわされるようになりました。
- 石高制…武士の知行(領地から年貢を取る権利)は石高で示されるようになりました。→大名や家臣の領地の規模が明らかとなり、石高に応じて軍役を負担する制度が整えられました。
- 荘園制度の否定…荘園領主や有力農民が持っていた土地の権利が否定され、荘園制度は完全にくずれました。土地の所有権と年貢の義務:耕作する農民に土地の所有権を認める一方、年貢をおさめる義務を負わせました。
刀狩
1588年、秀吉は刀狩令を出し、農民や寺社から刀、弓、鉄砲などの武器を取り上げました。
- 農民の武力による一揆を防ぐ。
- 農民をもっぱら耕作に従事させる。
兵農分離
検地と刀狩によって、武士と農民の身分の区別を明確にする兵農分離が進められました。兵農分離は江戸幕府に引きつがれ、近世の日本社会の基本を形づくりました。
- 武士…領地をはなれ、城下町に集められました。
- 農民…農村に住むこととされて、土地を捨てて武家に奉公したり、町人になったりすることを禁じられました。
- 商人・職人…城下町や港町に集められました。
海外貿易
豊臣秀吉は海外との貿易に積極的な姿勢を示しました。
- 渡航の奨励…京都,長崎,堺などの商人の海外渡航を奨励し、海賊を取りしまって貿易船の安全を図りました。
- 対外政策…朝鮮,高山国(台湾),ルソン(フィリピン)などに服属を求めました。
朝鮮侵略
豊臣秀吉は海外貿易を奨励し、朝鮮侵略とかじを取ります。その朝鮮侵略は朝鮮民衆の抵抗と明の救援があり失敗に終わります。1592年(文禄の役)と1597年(慶長の役)の二度にわたって、豊臣秀吉は朝鮮の侵略を命じました。
- 目的…明の征服を計画した豊臣秀吉は、朝鮮に協力を要請しましたが断られたため、朝鮮侵略を開始しました。
- 過程…豊臣秀吉の命令を受けた大名は釜山に上陸したのち、首都漢城(現ソウル)を占領し、一部は平壌に進みました。
- 抵抗運動…朝鮮民衆の義兵による抵抗運動、李舜臣(1545~98)が率いる水軍の活躍。明の援軍などによって、日本の軍勢は苦戦しました。
- 講和交渉…豊臣秀吉は、休戦して講和交渉を始めましたが、明を中心とする朝貢体制のもとでの講和に不満を持ち、交渉は失敗しました。
- 終結…豊臣秀吉はふたたび出兵を命じましたが、豊臣秀吉が病死したため、兵は引きあげられました。
朝鮮侵略の影響
- 朝鮮…多くの人が殺されたり、日本に連行されたりしました。
- 明…朝鮮への援軍のために、国力がおとろえました。
- 日本…武士や農民は重い負担に苦しみ、大名間の不和が表面化して、豊臣秀吉氏没落の原因となりました。
桃山文化
織田信長・豊臣秀吉が政権をにぎった約30年間を、信長の安土城や秀吉晩年の伏見城(城跡がのちに桃山とよばれる)にちなんで安土桃山時代とよんでいます。そして、この時期に栄えた文化を桃山文化といいます。桃山文化は、新興の大名や海外貿易などで活躍する大商人らの気風を反映して、豪華で壮大な活気に満ちた文化です。また、仏教の影響がうすれ、南蛮文化の影響を強く受けるようになり、庶民の間にも広まっていることも特徴です。
- 城…安土城、大阪城、姫路城など壮大な天守閣を持ちました。
- 絵画…狩野永徳の唐獅子図屏風など
- 茶の湯…堺の商人千利休が質素なわび茶を大成させます。
- 民衆の文化…浄瑠璃が琉球(沖縄県)から伝わった三線をもとにつくられた三味線に合わせて語られました。出雲の阿国が始めたかぶき踊りも流行しました。
- 衣服…小袖(こそで)が一般的になりました。庶民の衣服は、麻から木綿に。
桃山時代の建築・絵画
壮大な城や書院造の部宅の内部には、障壁画がえがかれました。建築や絵画には、桃山文化の特色がよく表れています。
- 天守閣…安土城・大阪城・姫路城など、そびえ立つ天守閣や石垣が築かれ、堀に囲まれた壮大な城は、領内の政治の中心となり、支配者の権威を示しました。
- 書院造…城内の御殿、公家や上級武士・大商人の邸宅などには書院造が取り入れられた。書院造を取り入れた城郭風邸宅として、豊臣秀吉が京都に造営した 聚楽第(じゃらくてい)が知られています。
- 障壁画…城や邸宅内部のふすまや屏風には、狩野永徳・山楽らの狩野派や長谷川等伯らの豪華な障壁画がえがかれました。
- 南蛮屏風…風俗をえがいた風俗画や、南査人の風俗や生活様式を題材にした南蛮屏風が流行しました。
桃山時代の茶道・芸能
室町時代に始まった茶の湯は、人名や大商人の間で流行していましたが、藩(大阪府)の商人の千利休が茶道(わび茶)として大成しました。
芸能では、出雲(島根県)の国が始めた歌舞後おとり(阿国歌舞伎)が流行し、歌舞伎のもとになりました。また、小歌(気軽に歌える歌詞)が流行ししました。さらに、琉球 (沖縄県)から伝わった一線を改良して三味線がつくられ、それに合わせて人形浄瑠璃が語られるようになりました。
南蛮文化
ヨーロッパの文化から影響を受けて成立した芸術や流行の風俗。
- 天文や医学、航海術など、新しい学問や技術が伝わりました。
- 狩野派の画家が、南蛮船入港の様子をえがく、ヨーロッパ風の絵画、宗教画。
- 活版印刷術が伝えられ、聖書、平家物語などの書物がローマ字で印刷されました。
- 衣服は、金のくさりやボタン、ヒダのあるえりがついたヨーロッパ風の衣服。十字架をかたどった首飾り。

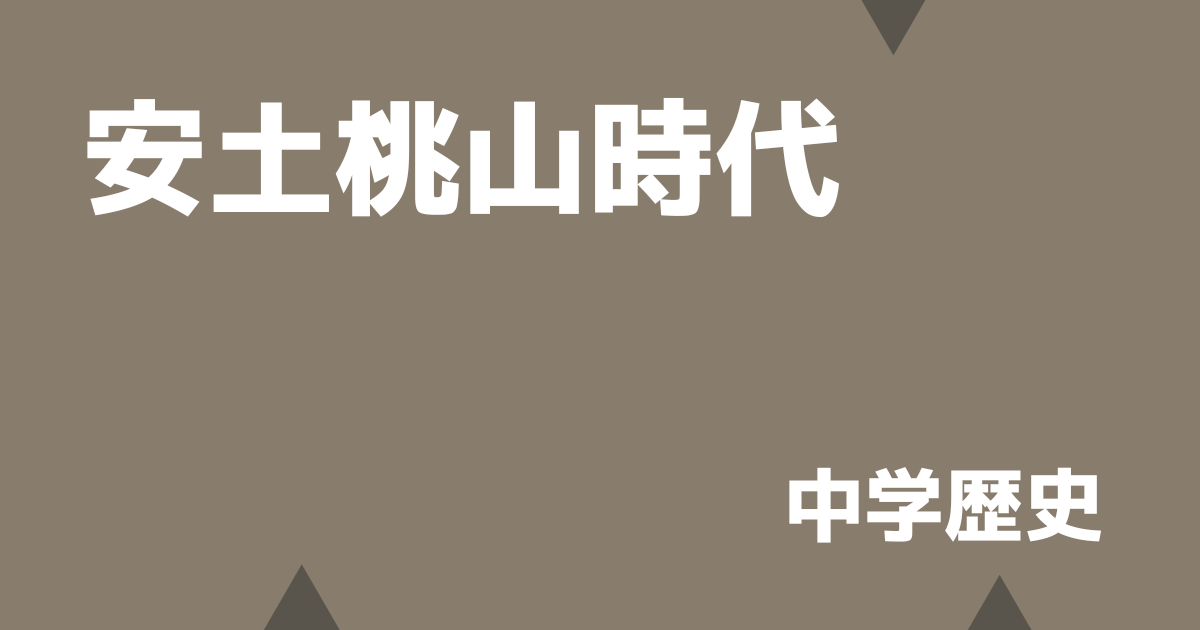
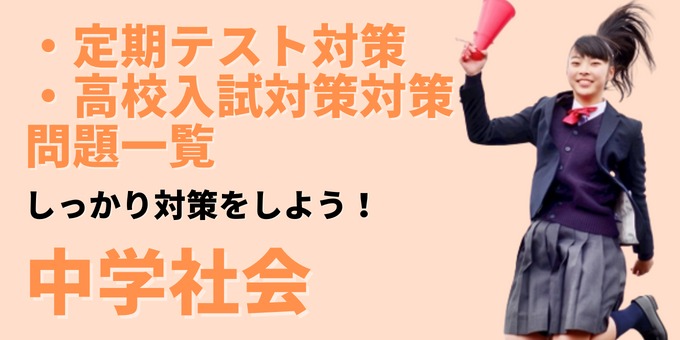
コメント