中学地理「世界の住居・衣服と食文化の変化」についてまとめています。世界の住居・衣服と食文化の変化に関して、世界のさまざまな住居・衣服の変化や食器や作法にもふれています。それでは、中学地理「世界の住居・衣服と食文化の変化」です。
世界の住居・衣服とその変化
さまざまな住居と変化ですが、気候や生活習慣にあった材料が使われ、形も多様です。
- 木が豊富にある地域…木造の住居が多いです。アメリカ合衆国などでは、丸太や角材などできた家が見られます。
- 日ざしの強い地域…厚い石で壁を作り、窓を小さくしてな暑さを防ぎます。イタリアなどでは石の外壁を白く塗った家が見られます。
- 雨が少なく、乾燥した地域…土を固めて作った家です。
- 家畜の群れを追って生活する人々…移動に便利な組み立て式の家です。モンゴルなど見られゲル(中国語ではパオ)です。
- 住居の変化…世界的に都市部を中心にコンクリート製の家も増えてきています。
さまざまな衣服と変化
衣服には、暑さ・寒さや日ざしから守る役割があります。気候に応じて、さまざまな形や素材の衣服が見られます。
- 暑い地域…風通しの良い木綿や麻の布などをゆったりまとう。
- 寒い地域…保湿性の良い動物の毛皮でできた衣服や手袋などを着用する。
衣服の変化
世界的にTシャツやジーンズが普段着として普及し、伝統的な衣装は、祭りや結婚式など特別な時のものに着る傾向が見られます。
世界の食文化と変化
世界各地で異なる食文化
主食(中心となる食べ物)は、その地域で作られている農作物と関わりが深いです。
- 米…日本・中国南部・東南アジアなど雨が多い地域が中心。炊いたり、おかゆにしたりするほか、粉を麺(ベトナムのフォーなど)にすることもあります。
- 小麦…米に比べて、雨が少ない地域で栽培しています。粉して、めん(イタリアのパスタなど)やパン(インドのチャパティなど)に。
- トウモロコシ…メキシコのトルティーヤは、粉にして練り、薄く伸ばして焼いたものです。また、米や小麦の栽培に向かないアフリカでは、湯でこねて、蒸し焼きにします。
- いも類…ヤムいもなどは、南太平洋の熱帯の島々で、ジャガイモなどは南アフリカで食べられています。
食器や作法
はし、フォーク、皿などの食器や食事の作法にも地域によって様々な違いがあります。
食文化の変化
世界各地の交流がさかんになるにつれて、他の地域の食文化も広まるようになりました。
暑い地域の暮らし
太平洋の島々での生活などになります。
ツバルやフィジーの自然
ツバルやフィジーは、オセアニア州の赤道付近にあります。一年を通して暑く雨が多い気候です。一年中、緑の葉がしげる熱帯雨林であり、ココやしなどの木が生えます。ツバルの島々は、サンゴ礁でできています。
暑い地域での島での生活
ツバルの伝統的な家は、熱帯雨林でとれる木の葉で屋根や穀物を作ります。壁が無く、高床で風が吹き抜けるようにして、熱や湿気を逃します。伝統料理は、ココやしの実からとれるココナツやパンの木の実、栽培したイモ、魚や貝などを材料にして蒸し焼きにしたり、焼いたりします。ココヤシの葉を編んだ皿に盛ります。
輸入品の増加と生活の変化
外国からの電気製品、衛星放送などの外国文化、コンクリートの家、外国産の米や加工食品などが普及。生活が便利になった一方で。ゴミ問題が発生しています。
寒い地域のくらし
シベリアの自然
シベリアは、ユーラシア大陸の北に広がる地域です。気温は、夏は20℃くらいまで上がりますが、冬は-30度以下になることもあり、雪と氷に覆われます。
厳しい寒さをしのぐ生活
多くの建物は、熱で永久凍土が溶けて建物が傾かないように、高床になっています。窓は2重~3重で、壁は極めて厚いです。外出時はトナカイや馬の毛皮でできたコート、ブーツ、帽子などを着用しています。作ることができるの農作物は限られます。短い夏の間に菜園で野菜を作り、保存食として漬物にします。冬は、漬物のほかに、さかなや牛、豚などの肉を食べます。
外来の文化と生活の変化
外国との結びつきが強まって、輸入食品が一年中豊富に売られるようなり、外国料理も定着しました。
乾燥した地域の暮らし
アラビア半島での生活
アラビア半島は、西アジアにありm砂漠が広がり雨が少ないため、草木がほとんどありません。しかし、自然に水が湧き出たり、地下水路や井戸で水を得たりしています。オアシスと呼ばれる場所があります。
乾燥した地域での生活
水は貴重で、オアシスで暮らす人々は、水路を洗濯や水浴びに共同で使い、使った水も農業など繰り返し利用しています。
農業と料理
小麦、なつめやしなど乾燥に強い作物を栽培し、オアシスの周辺では乾燥に強いいもやラクダなど遊牧が行われてきました。ラクダや羊の肉を焼いたり小麦を薄焼きのパンのようにして食べたりします。
衣類と住居
日中の強い日差しや砂埃から身を守るために、衣服は長袖で、丈が長いです。また、森林が少ないため、家の壁に土をこねて作った日干しレンガを使用しています。
水をめぐる生活の変化
原油が多くとれるサウジアラビアでは、原油を輸出した利益で国土を開発。海水を真水にする淡水化の技術を導入したり、深い井戸から電動モーターで大量の地下水を汲み上げたりして、吸水プールにためた後パイプで各家庭へ運んでいます。共同の水場の使用は減って、スプリンクラーを使えば大規模農業の可能になりました。一方で、大量の汲み上げで地下水がなくなる懸念もあります。
高地の暮らし
アンデス山脈との生活では、アンデス山脈の自然の赤道付近の高地なので、年間の気温の変化が小さいです。しかし、昼夜の気温差は20℃から30℃にもなります。
高地の生活
農業などは、山の急斜面や畑や牧草地に利用しています。標高2000から3000メートル付近ではトウモロコシ、それよりも高く、より寒いところでは、じゃがいもを作っています。農業に向かない4000メートル以上ではリャマやアルパカを放牧しています。
食事
畑でとれるジャガイモやトウモロコシが中心です。しかし、これらを市場で売り、標高の低い地域でとれる果物を購入することもあります。ジャガイモは、干して保存したものを戻して食べることもあります。
衣類と住居
アルパカなどの毛で作った衣類を重ね着して帽子をかぶり、寒さや強い紫外線を防ぎます。家は、壁は石や日干しレンガでつくられ、屋根はわらでできていて、熱が逃げないように窓が小さくなっています。
高地での生活の変化
電話線を引きにくかった高地でも通信用アンテナ設置は設置しやすいため、携帯電話が普及しています。町にはインターネットカフェも登場しています。また、世界遺産に登録されているマチュピチュなど、高地の自然や文化をめあてに外国からの観光客が増えたため、土産物を作る人々や土産物の店が増加していいます。さらに、道路が整備されてトラックが輸送の中心になった結果、リャマを使った昔ながらの輸送は、車の入れない高いところや細い道などにも限られるようになりました。
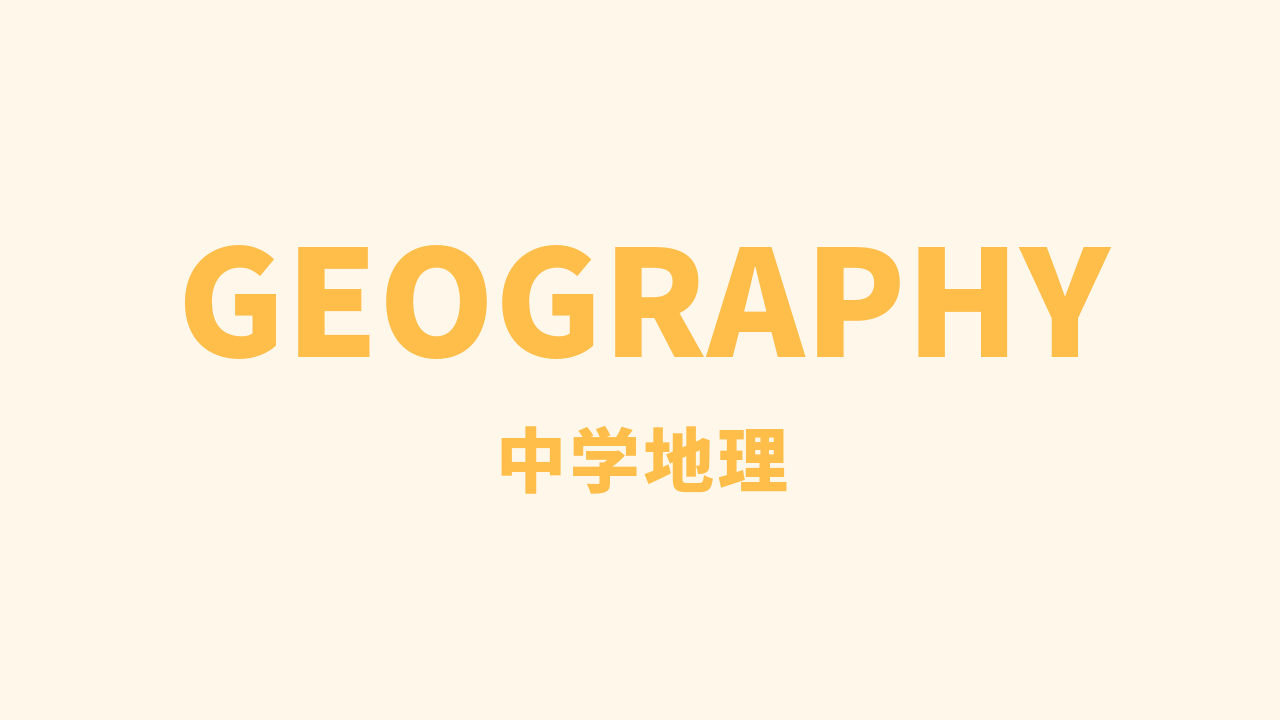
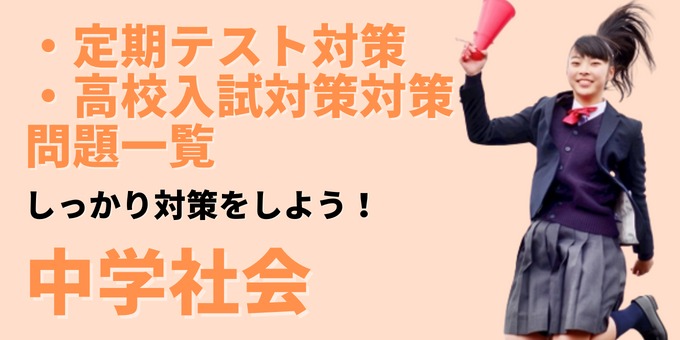
コメント