中3理科「浮力の求め方」についてまとめています。浮力のポイントは、物体にはたらく重力が浮力より大きいと物体は沈み、重力が浮力より小さいと物体は浮くということです。
浮力の要点
水中の物体に、はたらく上向きの力。どんな物体も水などの液体の中では、浮力がはたらきます。浮力は物体の上面と下面にはたらく圧力の大きさの差によって生じます。よって、物体が液体にすべて入っているときは、深さに関係なく浮力は等しくなります。
アルキメデスの原理
液体中(気体中)にある物体は、その物体がおしのけた液体(気体)の重さに等しい大きさの浮力を受ける。これが、アルキメデスの原理で、このアルキメデスの原理は物体の形が不定形をしていてもあてはまります。
ものの浮き沈み
物体にはたらく浮力がその物体にはたらく重力より大きい場合は液体より上に浮き上がり、小さい場合は、液体の中に沈む。アルキメデスの原理のより、浮力は物体がおしのけた液体の重さに等しいので、水より軽い液体、つまり密度が小さい液体の中に物体を入れたとき、浮力は水中に入れたときより小さい。
水中の物体にはたらくカの浮力の実験
- ばねばかりで、物体にはたらく重力の大きさを調べる。
- 物体を水に入れ、ばねばかりの値を読む。 物体を水に入れる深さを変えて行う。
- 物体の材質や体積を変え、1,2の操作を行う。
浮力の実験結果
- 物体を水中に入れたときのばねばかりの値は、物体にはたらく重力の大きさより小さくなった。
- 物体の深さを変えてもばねばかりの値は変化しなかった。
- 物体の体積を大きくすると、ばねばかりの値は大きく変化した。
浮力の実験からわかること
- 空気中ではかった物体の重さから水中に入れたときに ばねばかりが示す値を引くと浮力が求められる。
- 物体の体積が大きいほど、物体にはたらく浮力は大きくなる。
浮力の求め方
- 浮力=空気中での重さー水中でのばねばかりの値
浮力のその他の求め方
- 下面にはたらく水圧の大きさ-上面にはたらく水圧の大きさ=浮力
- 空気中での物体の重さ-水中での物体の重さ=浮力
- 物体がおしのけた水の体積(水につかっている体積)=浮力
【問題】浮力の練習問題
水中の物体にはたらく力を調べるために、次のような実験を行った。 あとの問いに答えなさい。
【実験】
- 実験1:40gの物体をばねばかりにつり下げ、目もりを読む。
- 実験2:物体をばねばかりにつるしたまま水中に入れ,物体が全部水に入ったときの目もりを読む。
(1) 実験1でばねばかりの目もりは何Nを示していたか。ただし、100 gの物体にはたらく重力の大きさを1N とする。
(2) 実験2で、ばねばかりの目もりは 0.3 N を示していた。水中でこの物体にはたらく上向きの力は何Nか。
(3) (2)のような水中ではたらく上向きの力を何というか。
(4)この物体を実験2よりさらに深く沈めたとき,(3)の力の大きさはどうなるか。
(5) (3)の力は,物体の体積を大きくするとどうなるか。次のア~ウより選び、記号で答えなさい。
ア 変わらない イ 大きくなる ウ 小さくなる
【解答】浮力の練習問題
(1)0.4N
(2)0.1N
(3)浮力
(4)変わらない
(5)イ
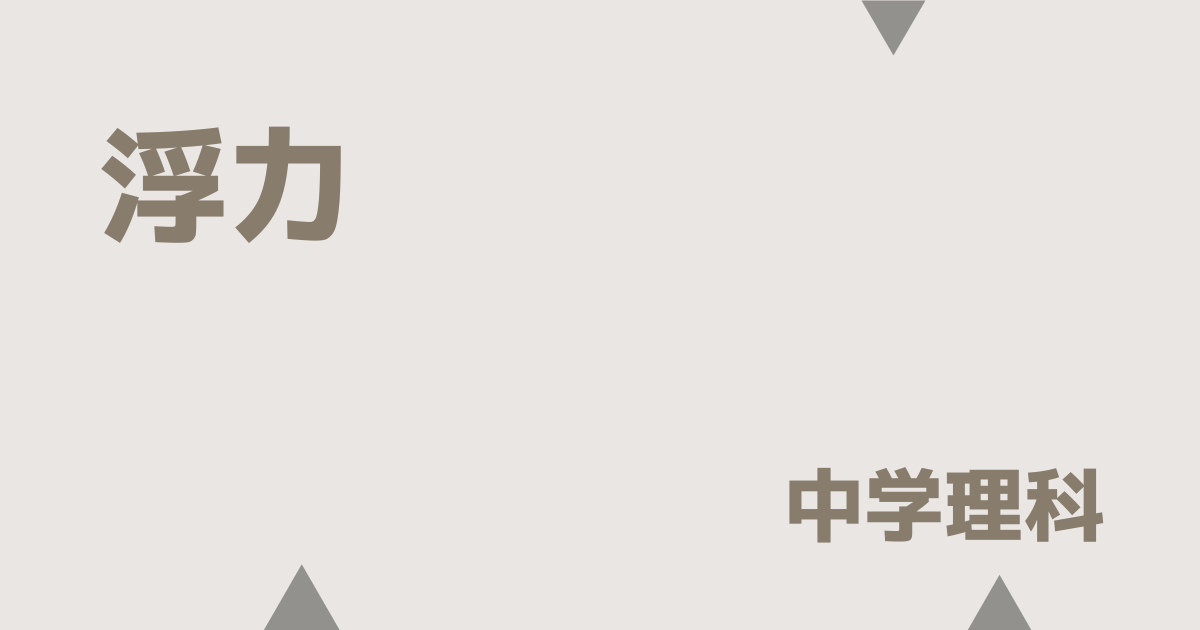

コメント