【中学歴史】建武の新政・南北朝時代についてまとめています。
建武の新政の要点
鎌倉幕府滅亡の翌年(1334年)、後醍醐天皇は年号を「建武」と改め、自ら政治をとった。これを建武の新政という。後醍醐天皇は、公家と武家を統一した天皇中心の政治を理想とし、公家・武家の区別なく役人に任じることを方針とした。しかし、実際は理想に反して、公家を重視した政治が行われた。
- 中央…摂政・関白が廃止
- 地方…将軍府や鎌倉将軍府などの機関がおかれた。
武士への恩賞
武士には恩賞が少なく、そのうえ新しい税を課し、それまでの武士社会の慣習を無視した政策を進めたため、政治の混乱がおこり、公家と武士の対立を招いた。こうして後醍醐天皇の政治に不満が高まり、とくに武士は、武家政治の復活を望むようになった。
南朝と北朝の争い
武家政治の復活をねらう足利尊氏は、武士の不満を受けて、1335年、対立する新田義貞の打倒を名目にして兵をあげ、京都に攻めこんだが失敗した。いったん九州にのがれた足利尊氏は、1336年に再び兵をあげ、京都を占領した。そのため、後醍醐天皇は吉野(奈良県) にのがれ、建武の新政は2年余りでくずれた。
南北朝時代の要点
この1336年、後醍醐天皇は吉野に南朝をおこし、新田義貞・北畠親房のほか、地方の武士を味方にして政治を行い、足利尊氏は、京都に光明天皇を立て北朝を開かせた。諸国の武士は、2つの朝廷のどちらかについて争うようになり、約60年にわたって動乱が続いた。この時代を南北朝時代という。やがて、有力な守護が北朝 側につくようになり、南朝の勢力はおとろえていった。
- 北朝…足利尊氏が、京都に新しい天皇を建てます。
- 南朝…後醍醐天皇は、吉野(奈良県)にのがれます。

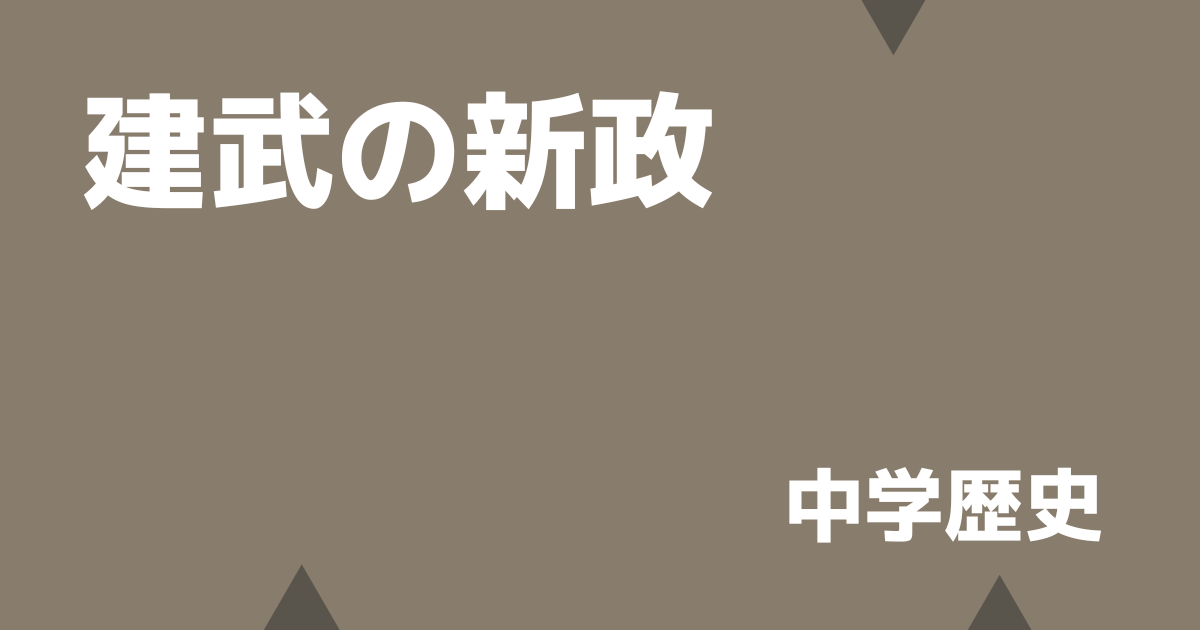
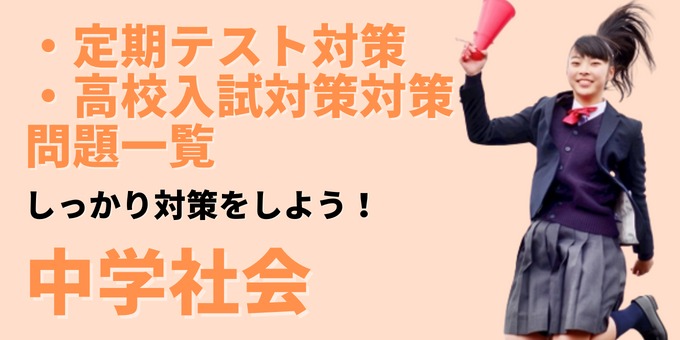
コメント