中学理科「プラスチックの性質と用途」についてまとめています。
プラスチックの性質
- 電気・熱を伝えにくい…テレビ・エアコンなどの電化製品の外枠や食器などに利用される。
- 薬品に対して安定で変質しにくい…酸・アルカリなどの薬品や水などにもとけないため、手術用の手袋、ゴミ袋、水などを通すパイプなどに利用される。
- さまざまな形に成形できる…さまざまな形の部品やプラモデルに利用される。
- 軽い…ガラス製のびんの代わりに、PETボトルを用いることによって、割れにくく、軽くなった。
おもなプラスチックと用途
石油などを原料としてつくった、成形しやすい物質。加熱すると燃えるが、そのようすは、酒類ごとに異なります。燃えると二酸化炭素を発生するので、どれも有機物となります。
| プラスチック名 | 略語 | 浮沈 | 特長 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン | PE | 水に浮く | 水や薬品に強い | レジ袋、まな板、食品用ラップ |
| ポリエチレンテフタラート | PET | 水にしずむ | うすい透明な容器をつくりやすい | 飲料のプラスチックボトル、衣料用の繊維 |
| ポリスチレン | PS | 水にしずむ | 発泡材は軽い | 食器 |
| ポリプロピレン | PP | 水に浮く | 熱に強い | 弁当箱、電気器具、ボトルキャップ、フィルム状にして包装や建材 |
| ポリ塩化ビニル | PVC | 水にしずむ | 燃えにくい | 水道管、ゴムホース、消しゴム、ロープなど |

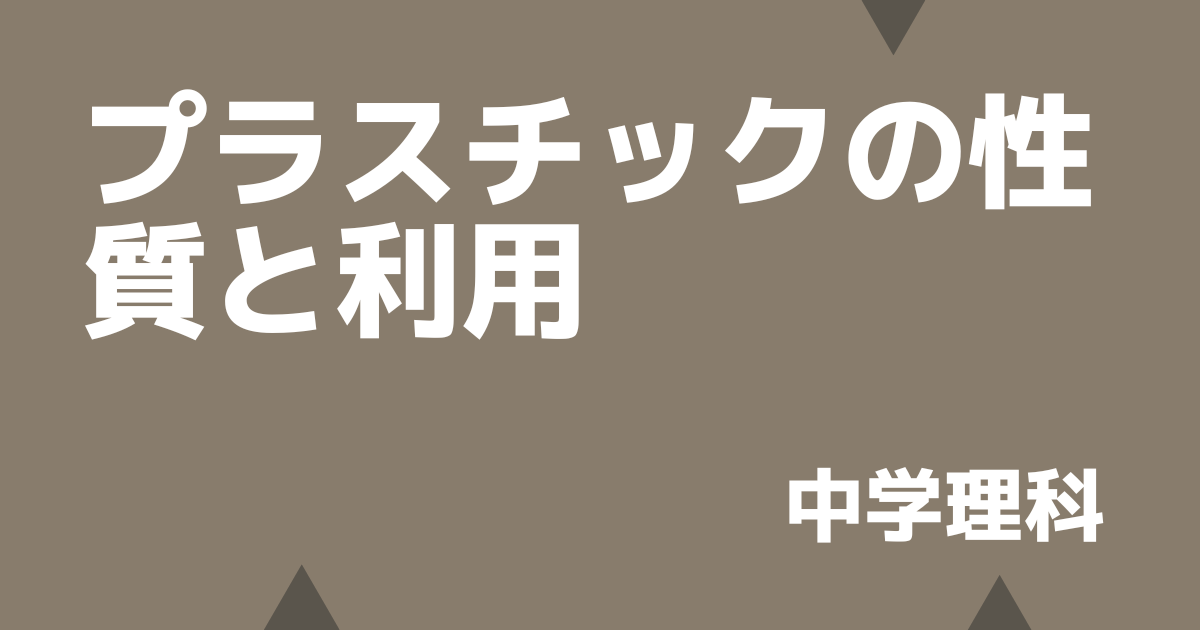

コメント