中3社会科の【中学公民】前期期末テスト対策予想問題(解答付き)です。
※記号がついている語句は記号で答えなさい。
※教科書、プリント等に漢字で記載されている語句については漢字で答えなさい。
※人物名は漢字指定とします。
前期期末テスト対策予想問題(中学公民)
【問1】次の問いに答えなさい。
(1) 大阪空港周辺の民家の上をすれすれに 飛行機が飛んでいる地域がある。その空港周辺の住民は国を相手取り裁判を起こしていたが、どのような人権が 侵害されたと訴えていたのか。
(2) 次の文にあてはまる「新しい人権」を答えなさい。
(3) 医療において、自己決定権を尊重するために行わ れている「治療を受ける患者のために重要とされている、じゅうぶんな説明にもとづく同意」のことを何といいますか。
(4) 国際的な人権保障の実現のために、国境を越えて連帯して活動する「国境なき医師団」などの民間の組織を何といいますか。
【問2】次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。
(1) 文章中のA・Bにあてはまる語句を答えなさい。
(2) 文章中の下線部アについて、二院制をとる理由としてあやまっているものを、次のア~エから 1つ選び、記号で答えなさい。
ア 審議を慎重に行うため。
イ 国民のさまざまな意見を国会に反映させるため。
ウ 参議院のほうが衆議院に比べ歴史があるため。
エ 一方の議院の行き過ぎを抑えるため。
(3) 文章中の下線部イについて、なぜ衆議院のほうに優越が認められているのでしょうか。「解散」「任期」「意思」という語句を使って簡潔に説明しなさい。
前期期末テスト対策予想問題(中学公民)の解答
【問1】
(1)環境権(静ひつ権)
(2)プライバシーの権利
(3)インフォームド・コンセント
(4)NGO(非政府組織)
【問2】
(1)A最高 B立法
(2)ウ
(3)「任期」が短く 「解散」もあるので、国民の「意思」がより反映されやすいから。
(4)1.A常会 B特別会 2.イ 3.「衆議院」が 「出席議員」の 3分の2以上の 多数で再可決する。
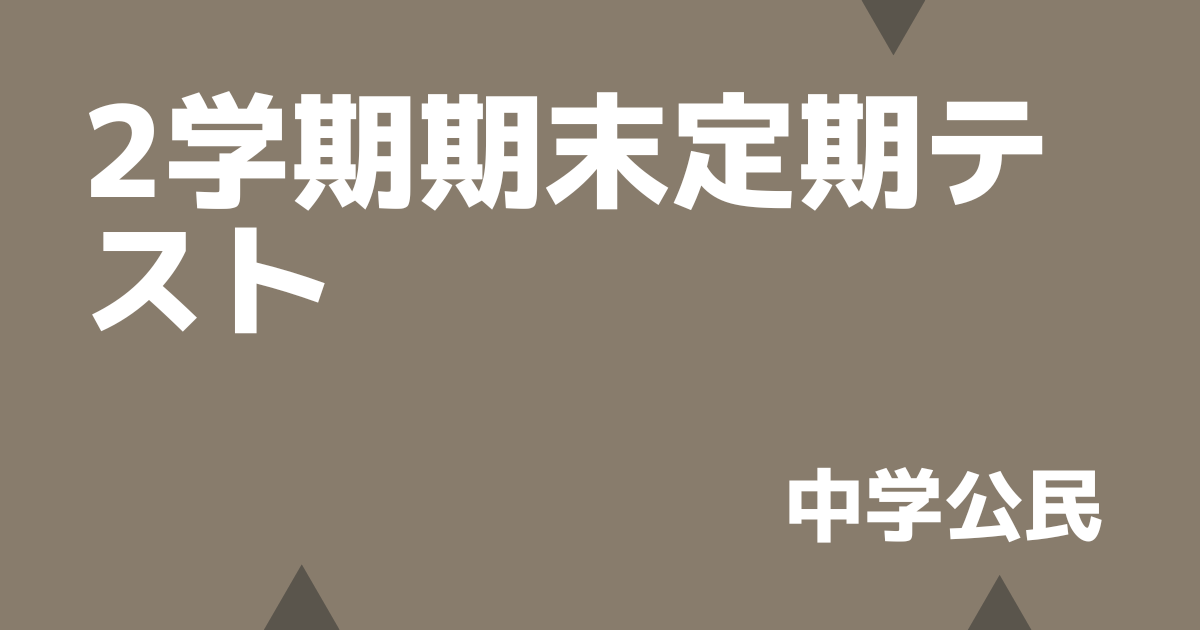
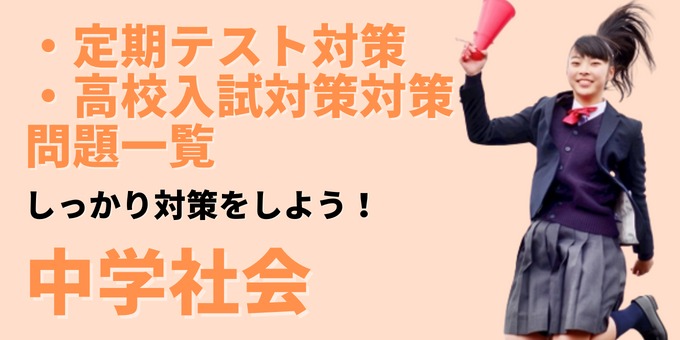
コメント